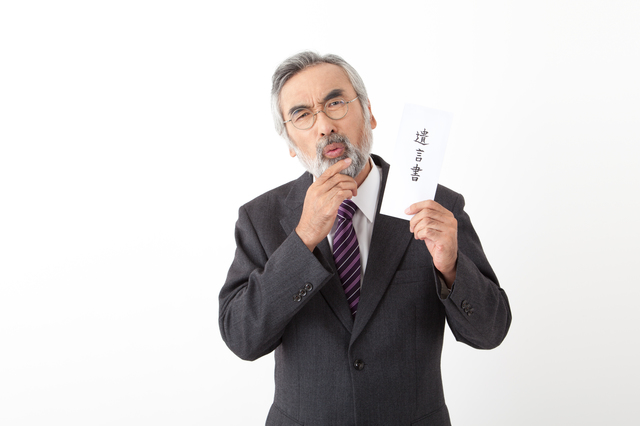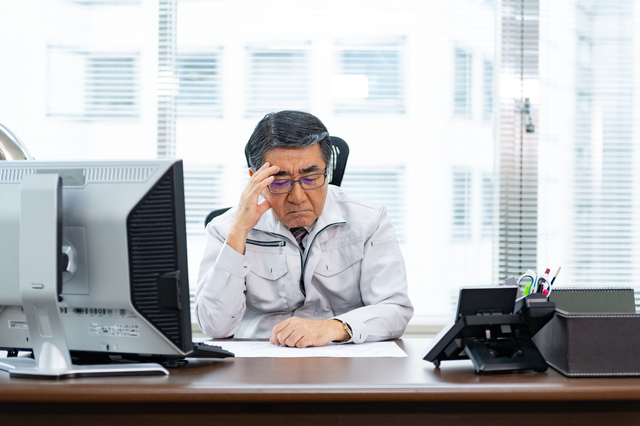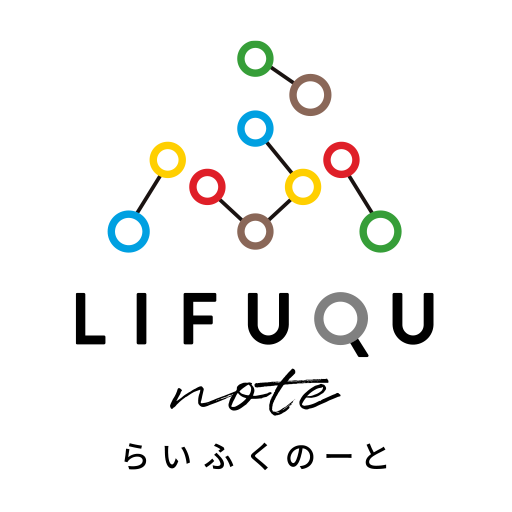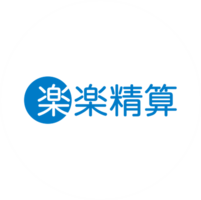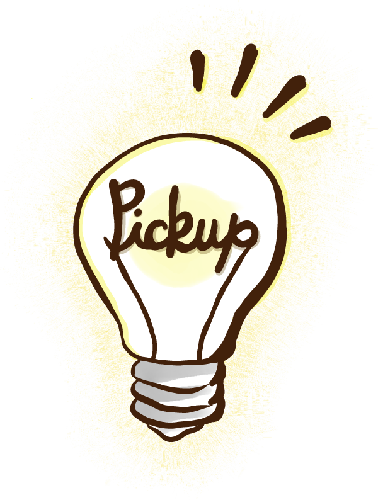松田聡子
群馬FP事務所代表、CFP®、証券外務員二種、DCアドバイザー松田聡子
群馬FP事務所代表、CFP®、証券外務員二種、DCアドバイザー国内生保で法人コンサルティング営業を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在は法人向けには確定拠出年金の導入コンサル、個人向けにはiDeCoやNISAでの資産運用や確定拠出年金を有効活用したライフプランニング、リタイアメントプランニングを行っている。
Their Links:
Website
続きを読む >