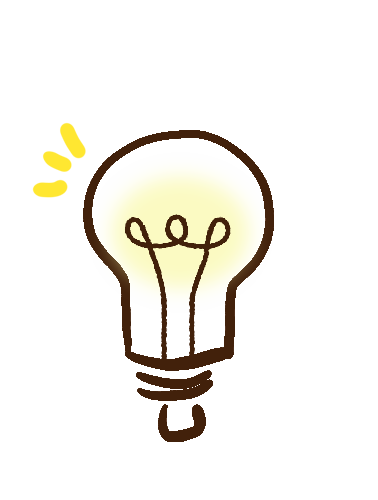LIFUQUnoteらいふくのーとサポーターズ
西日本シティ銀行

CFP®・宅地建物取引士(未登録)・住宅ローンアドバイザー・証券外務員2種・DCプランナー2級・エクセルVBAエキスパートなど
CFP®・宅地建物取引士(未登録)・住宅ローンアドバイザー・証券外務員2種・DCプランナー2級・エクセルVBAエキスパートなど
2006年2月にファイナンシャルプランナー(FP)として独立、個人相談をはじめ、カルチャーセンター講師やFP資格講師・教材作成、サイト運営・執筆など、FPに関する業務に携わり15年以上経つ。商品販売をしない中立公正な立場で、相談者の夢や希望をお伺いし、ライフプランをもとにした住宅ローンや保険などの選び方や家計の見直しを得意とする。執筆でも、わかりやすく伝えることはもちろん、情報を精査し、消費者・生活者側の目線で書くことにこだわる。