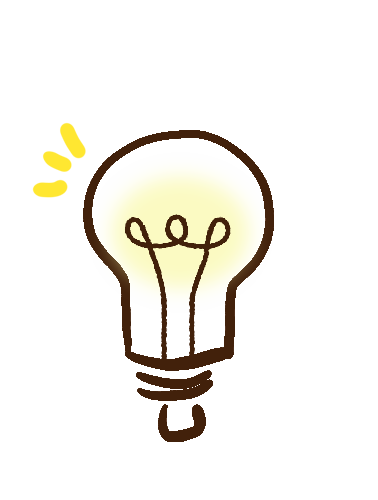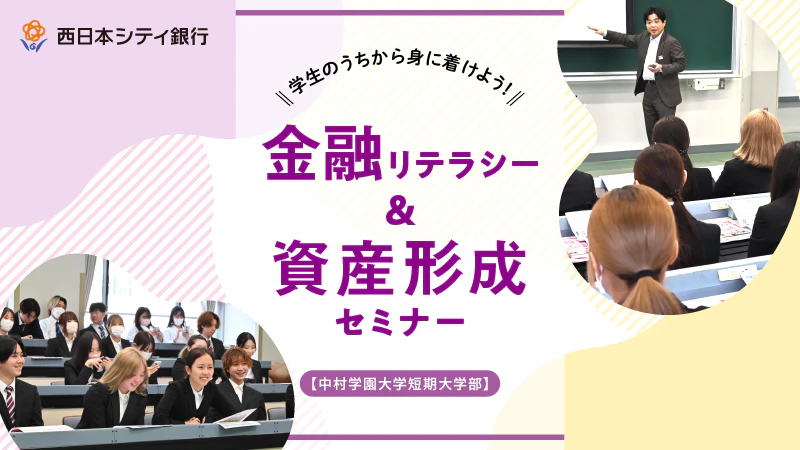HSP(繊細さん)とは?特徴や対処法を解説!診断テストやおすすめ本もご紹介

HSPとは「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の略称で、非常に繊細な人を指します。最近では書店に多くの本が並んでいたり、有名人・芸能人がHSPであることを公表したりと、HSPという言葉を見聞きしたことがある人も多いのではないでしょうか?
では、HSPにはどのような特徴があり、どう対処すればよいのでしょう。HSPの基礎知識について、簡単にできるセルフチェックとともに紹介いたします。
目次
HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)とは?どんな意味?

HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)とは
HSPとは、周囲からの刺激を受けやすい「繊細な人」を意味する言葉です。環境や性格といった後天的なものではなく、生まれ持った気質であるとされています。
非HSPなら気にならない刺激にも敏感に反応してしまうため、生きづらさやストレスを感じやすい傾向にあります。
HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の意味:繊細な性格特性(気質)を持つ人
HSPは性格特性(気質)のひとつであり、大まかにいうと「繊細な人」を指すもので、米国の心理学者であるエイレン・アーロン博士が世界に広めた概念です。他人の言動や感情への共感性が高い、音や光などの環境からの刺激に対して敏感などの特徴が挙げられます。
人口の2割ほどがHSPといわれるほか、人間以外の動物にもHSPの傾向が見られることがあります。HSPだと集団生活がしんどくなったり、生きづらさを感じたりすることもあります。
HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の特徴:刺激に対する敏感さ・繊細さ
HSPの特徴は、空気を読み過ぎて疲れてしまうことや、刺激に対して敏感となりやすい傾向があります。また、先ほど触れた音や光のほか、臭いや身体感覚、気候など、五感で体感する刺激に敏感だとされています。
映画や漫画などに感情が入ってしまったり、人の考え方に影響されたりするケースもあります。このほか、人込みで気疲れしてしまう、自己否定してしまうなど、繊細であるがゆえにストレスがかかってしまうと考えられます。
HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)という病気はなく、あくまでも「気質」であり、治療法はない
HSPは一見すると病名のようですが、HSPはあくまでも性格特性(気質)であり、精神医学上の概念ではありません。一般的に、「精神疾患」として診断名が付く場合、「DSM-5」という精神疾患の国際的な診断基準に基づいて判断されます。HSPの場合は、この「DSM-5」に現在のところ記載がなく、「精神医学上の概念」というよりは「心理学上の概念」であると考えられます。
したがって、HSPは何らかの病気・障害というよりは、人が誰しも持っている性格特性(気質)と考えるのが適切でしょう。性格特性(気質)ということは、病気・障害のように「薬等を使って治療する」というよりは「日常の中でどう付き合っていくか」がより重要です。考え方や環境を変えるなどの工夫が必要といえるでしょう。
HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)を「繊細さん」と呼ぶことも
HSPは忌避すべき存在ではなく、向き合っていくべき存在です。したがって、親しみをもって接する必要があります。親しみを込めた呼称のひとつに「繊細さん」があります。この呼称は、山口由起子さんが名付け親で、最近では武田友紀さんの著書が人気ですね。
■「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本
■今日も明日も「いいこと」がみつかる 「繊細さん」の幸せリスト
■仕事、人間関係の悩みがスーッと軽くなる! 「繊細さん」の知恵袋
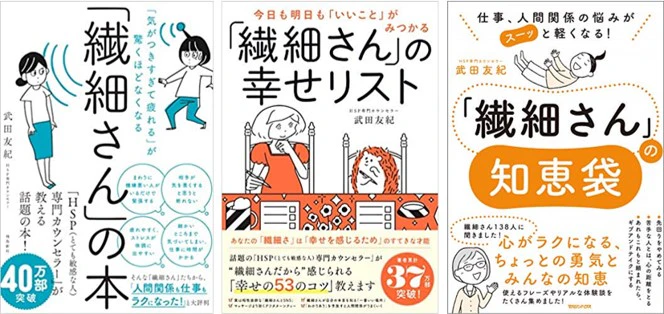
これらの書籍を書店等で目にしたことがある人も多いのではないでしょうか?
武田友紀さんいわく、「繊細さを克服すべき課題と捉えるのではなく、いいものとしてとらえる。自分の気質を肯定し活かすことで、元気に生きていける」とのことで、HSPに対する基本的な向き合い方を端的に示した言葉といえるでしょう。
Amazonの電子書籍が読み放題!
Kindle Unlimitedの詳細はこちら
HSPの特徴・あるあるとは?

どのような特徴を持つ人がHSPに当てはまるのでしょうか。ここでは、HSPならではの特徴や具体例(あるある)を8つ紹介します。以下の症状やケースに多く当てはまるほど、HSPである可能性が高いといえるでしょう。
①自己否定しやすい
HSPは自己肯定感(自分を価値ある存在だと受け入れている感覚)が低く、いつも自分を責めてしまう傾向にあります。
たとえば、周囲に怒っている人がいると、自分にまったく非がなかったとしても「自分の責任ではないか」と考えてしまうことがあります。
②雑談やうわさ話、大人数の集まりが苦手
HSPは1対1で相手と深く関わり合うことを好む傾向があり、雑談やうわさ話といった表面的な会話や大人数の集まりは苦手な人が多いです。
周囲の騒音や相手の表情・しぐさに過剰に反応してしまうため、どう振る舞えばよいか分からず、すぐに疲れてしまうことがあります。
③小さな音が気になって集中できない
HSPは感覚が敏感であるため、小さな音が気になって仕事や勉強、読書などに集中できないことがあります。
たとえば、マウスやキーボードをたたく音、時計の針がカチカチと動く音、周囲の人々の話し声・足音などが挙げられます。非HSPには気にならない音であっても、音の刺激に敏感なHSPには気になってしまうのかもしれません。
④物事を決めるのに時間がかかる
HSPは自分に自信がなく、他人を優先してしまうため、物事を決めるのに時間がかかる傾向があります。自分より他人を優先し、必要以上に相手の気持ちを読もうとしてしまうことが原因の一つだと考えられます。
⑤頼まれたことを断れない
HSPは相手を思いやる気持ちが強く、他人から頼まれたことを断れないという特徴もあります。
自信のなさから自己主張できなかったり、いろいろ考えて即答できなかったりして、仕方なく受け入れてしまうケースもあるでしょう。その結果、自分の時間がなくなってしまい、後で苦労することもあります。
⑥急に予定が変更になるとパニックになる
相手の都合や天候などを理由に、あらかじめ決まっていた予定が急に変更になると、HSPはパニックになることがあります。
細かいことに気づきやすいHSPは、複数の業務を同時並行でこなすマルチタスクは苦手です。急に予定が変更になると過剰に反応してしまい、どのように行動すればよいかわからなくなってしまうのです。
⑦一人を好む
HSPは刺激がない環境を求める傾向があり、自分の世界にいると落ち着きを得られることから、一人を好む特徴があります。人付き合いも大人数と付き合うより、少人数と深く関わることを望む人が多いでしょう。
⑧直感力がある
HSPは物事の本質や周囲の雰囲気を感じとる能力が高く、直感や予感が鋭い特徴があります。
たとえば、「いつもより元気がない」など、ちょっとした表情の違いから相手の変化に気づくことができます。また、何らかの意思決定を行う際に、直感に従うことですぐに適切な判断を行える人もいるでしょう。
あなたはHSP?診断テストでセルフチェック!

もしかしたら自分はHSPではないかと思ったら、まずは簡単な診断テストでセルフチェックをしてみましょう。下記の項目に当てはまる数が多いほど、HSPの気質を持つ可能性が高いといえます。仕事やプライベートの場を思い起こしながらチェックしてみましょう。
チェック項目①:思考が複雑で、深慮の上で行動する
調べごとを入念にしたり、お世辞にすぐに気付いたりするケースが挙げられます。また、行動する前に熟慮して踏み出せないような人が当てはまります。
チェック項目②:刺激に対して疲れやすい
「刺激に対して疲れやすい」とは、混雑する場所が嫌いであったり、人付き合いに疲労感を持ちやすかったり、他人の言動に影響を受けやすかったりすることが典型例として挙げられます。
また、ちょっとしたことに対してオーバーリアクションするケースや、感動しやすく涙もろいケースなども当てはまります。
チェック項目③:相手の気持ちに影響されやすい
映画やドラマなどの登場人物に感情が入ってしまう、他人が叱責されているときに自分も叱責されている気持ちになるなどが挙げられます。
また、相手のしぐさや表情を読み取り、マイナス感情を持たれているのではないかと気にしてしまう傾向があります。このほか、話ができない動物や幼児などの考えを読み取ることができるのも特徴です。
チェック項目④:あらゆることに対して感受性が強い
たとえば、家電製品のブーンという音が耳についたり、明るさが苦手であったり、体臭や口臭に敏感であったりします。喫煙者が吐く煙や、身体に付いたタバコの臭いで気持ちが悪くなることなどが挙げられます。
このほか、カフェインや添加物への反応、直感が当たる、服の肌触りが気になるなど、さまざまなことに敏感という特徴があります。
チェック項目⑤いつも自分を責めてしまう
自己肯定感が低く、いつも自分を責めたり、否定したりすることが挙げられます。
自分より他人を優先してしまう特徴があり、責任感の強さゆえに「自分が悪いのではないか」「もっとかんばらなければ」と考えてしまう特徴があります。小さなミスであっても、自分を過度に追い込んでしまいがちです。
チェック項目⑥怒りをうまくコントロールできない
普段は周囲に合わせて自分を抑え込んでいる分、一度怒りのスイッチが入ってしまうとうまくコントロールできなくなる特徴があります。
相手に怒りをぶつけるのではなく、自分の殻に閉じこもって相手とのコミュニケーションを避けるケースもあります。
チェック項目⑦直感や予感がよく働く
感覚が敏感であることから直感や予感が強く、未来のことや物事の本質、周囲の雰囲気などを察知する能力があります。
内向型の性格の人が多く、直感的にたくさんの情報を得られるため、周囲の人が気づかないようなことも把握できるのが特徴です。
知っておきたいHSPの基礎知識

HSPは大人に対する呼び方!子供のHSPはHSCと呼ぶ
HSPは「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」だと紹介しましたが、実はこれは大人だけの呼び方です。子どもの場合にはHSCと呼び、HSCとは「Highly Sensitive Child(ハイリー・センシティブ・チャイルド)」の略称です。
いずれにせよ、特徴は同じであるため、大人と子どもで呼び方を変えているものだと理解しておくとよいでしょう。HSCの子どもは「育てにくい」と思われることがありますが、HSCの特徴を理解して広い心で接することが大切といえます。
HSPとうつ病・適応障害との違い
「HSP=うつ病・適応障害」ではない!
HSPの人は、自分のことをうつ病だと感じてしまうケースがありますが、「HSP=うつ病・適応障害」ではありません。HSPが病気ではない一方で、うつ病は「心の風邪」と呼ばれ、早期治療が必要なものです。
ただし、HSPであることから、結果的にうつ病や適応障害になるケースはありえます。ちなみに日本人が月曜日にブルーな気持ちになるのは、一種のうつ病だといわれています。
HSPかな?と思ったら、早めに受診することが大切
軽度のうつ病であれば休養だけで改善することもありますが、慢性化や重症化してしまうと、休養だけでは治りにくいと考えられます。ひと口にうつ病といっても症状の幅が広いため、早めに心理カウンセリングや精神科などを受診して改善を目指しましょう。
HSPと発達障害との違いは?
HSPは発達障害とも混同されるケースがあります。発達障害とは注意力や衝動性、多動性の問題があり、注意力が散漫になりがちとされています。また、衝動的な行動をしてしまうケースもあります。
発達障害もある種の個性と捉えるケースがあるため混同されやすいですが、内面の繊細さを表現するHSPと、先天的不得手を持つ発達障害は別物だといえます。
Amazonの電子書籍が読み放題!
Kindle Unlimitedの詳細はこちら
あわせて読みたい
■産後うつの症状とは?チェックリスト&夫婦で覚えておきたい原因・対策・予防法
■おすすめ睡眠グッズを紹介!眠りの質が上がる快眠アイテム6選
自分がHSPの場合の対処法は?

①カウンセリングを受ける
HSPの対処法として、カウンセリングを受ける方法が挙げられます。日本ではカウンセリングを受ける習慣がまだまだありませんが、アメリカなどでは一般的となっています。生きづらさを感じるなら、一度カウンセリングを受けてみるとよいでしょう。
心理カウンセラーへ気軽に相談してみる
心理カウンセリングと聞くと、「専門的な資格を持っている先生に対し、精神疾患者が相談する」というイメージが強いかもしれません。しかし、心理カウンセラーは心理資格を必置としていないため、お悩み相談のような軽い相談も可能です。
反対に、精神疾患の場合は医師が診察する必要があります。したがって、HSPの場合は、カウンセラーに相談するほうが向いているともいえます。まずは楽な気持ちで相談してみましょう。
心配なときは有資格者に相談する
心理カウンセラーは必置資格でないことから、相談したカウンセラーがスキルに乏しいことも考えられます。心配な場合は、公認心理師や臨床心理士など心理系の資格を保有している人に相談しましょう。
②自分にとっての安全基地をつくる
安全基地=心の拠りどころ
自分にとっての安全基地をつくるというのもよい方法といえます。安全基地とは、心の拠りどころとなる存在のことです。
子育てなら、親との信頼関係が盤石だからこそ、子どもはすくすく成長できるといえるでしょう。つまり、子どもにとって親は安全基地だと考えられます。
「安全基地」に依存的にならないように注意
親以外に、恋人や親友、メンターなども安全基地として挙げられます。また、先述のカウンセラーを拠りどころとしてもよいでしょう。ただし、相手に依存的になると対等の関係でいられなくなるため、その点には注意が必要といえます。
③無理のない範囲で刺激に慣れる
HSPの場合、刺激を回避し続けていると、かえって刺激に弱くなってしまうと考えられます。反対に、活発な活動を続けることで刺激に慣れて、少しずつ和らいでいくこともありえます。
無理に刺激を受け続けるとストレスとなってしまいますので、無理のない範囲を超えないように活動を続けることが大切といえます。
刺激を緩和するアイテムの活用も視野に
視覚や聴覚からの刺激で疲れてしまうといった人もいるのではないでしょうか。そういった場合には、アイマスクや耳栓の活用も有効的です。常時着用は難しいかもしれませんが、集中したいときや落ち着きたいときなど、ここぞというときに活用することを検討してみるのも一手でしょう。まずは、使い捨てのものから試してみてはいかがでしょうか。
参考1:アイマスク 目隠し 安眠 遮光 眼精疲労 快眠 昼寝 睡眠 シルク素材 軽量 バンド2本 圧迫感なし ARIALK (1 ブラック)
参考2:色がきれいな使い捨て耳栓 MOLDEX スパーク・プラグ (10ペア)
④人との距離感を保つ
人に影響されすぎたり、人に振り回されたりするのであれば、距離感を保つのも一つの方法です。好きな人とだけ付き合う、人と会う頻度を少し減らす、SNSの利用を制限するなど、付かず離れず程度に割り切ってみましょう。
人間関係をリストアップして棚卸する
今の人間関係が苦痛なのであれば、人間関係の棚卸もおすすめです。自分の夢や目標と無関係な人、利害関係がない人に誘われても応じないようにしましょう。今の自分や将来の自分にとってプラスの人間関係かどうかがチェックの基準となります。
一人ひとりとの付き合い方や頻度を設定することで、無理のない範囲での人付き合いがしやすくなるでしょう。
⑤スルーすることを覚える
気持ちを楽にするためには、スルーすることを覚えるのも有効といえます。他人の言動を真に受けて振り回される場合、実は気にするような内容ではないケースもあります。
笑顔で大人な対応をし、心では相手にしない方法を身につけられれば、気持ちの和らぎ方が違ってくるでしょう。
ミラーニューロン効果を防ぐ
人間の脳は、あくびが伝染するのと同様に、人の感情が伝染する性質があります。このことをミラーニューロンといいます。
イメージで自分の周りにバリアを張ると、ミラーニューロン効果をシャットアウトできるとされています。これにより、相手に振り回されることを回避しやすくなるでしょう。簡単にできる方法ですので一度試してみてください。
⑥自分が何に敏感なのかを知る
刺激に対する敏感さは人それぞれ異なります。HSPである自分に対処するには、自分がどんな刺激に対して敏感なのかを知り、その刺激をなるべく避けることが大切です。
たとえば、人混みが苦手なら休日は一人または家族だけでのんびり過ごす、添加物が苦手なら食事内容に気を配るなど、自分に合った対策をとることを心掛けましょう。
日記やメモをつける
その日の行動や食事、そのときの体調や反応を日記やメモとして残しておくと、自分がどんな刺激に対して敏感に反応するかを知るきっかけになります。
また、気持ちを文字に書き出すことで自分を客観視することができ、気持ちが落ち着く効果も期待できます。
⑦無理に改善・克服しようとせず、HSPである自分を受け入れる
HSPは性格ではなく、生まれ持った気質です。無理に改善・克服しようとせず、ありのままの自分を受け入れる努力をすることも対処法の一つといえます。
HSPは「刺激に敏感で疲れやすい」「他人の影響を受けやすい」といったネガティブなイメージが強いかもしれません。しかし、「直感力がある」「周囲に対して気遣いができる」といったプラスの面もあります。
弱いところを隠そうとするのではなく、自分の弱さを受け入れて、今の自分にOKを出すことを心掛けましょう。
自分のよいところに注目する
自己否定をやめて、自分のよいところに注目する習慣をつけると、気持ちが軽くなる効果が期待できます。
具体的には、その日にあったよいことを3つ書き出す、その日によかったことを思い浮かべながら眠るといった行動がおすすめです。数か月程度続けると、自分を責める気持ちが減っていることに気づくでしょう。
⑧心の境界線を意識する
自分と他人との心の境界線を意識すると、生きづらいという感覚が少し解消されるかもしれません。
HSPは他人との境界線が薄いことから、周囲の影響を受けやすい傾向にあります。「自分は自分、他人は他人」「自分のことは自分で決める」という強い気持ちを持ち、他人との境界線を引くことを意識しましょう。
相手がHSPの場合の向き合い方は?

①相手がHSPの場合の対処法①:理解を示す
もし自身の周りにHSPの人がいれば、理解を示すことが大切といえます。HSPは繊細であるため、不用意な言動で傷つく可能性があります。先述したHSPの特徴に配慮して、相手の尊厳を大切にする姿勢を持ちましょう。
②相手がHSPの場合の対処法②:適切に褒める
人は、褒められると脳の扁桃核という部分が心地のいい状態になります。扁桃核が心地のいい状態になると、大脳辺縁系という感情の脳がプラス思考になるため、相手は喜びを感じやすくなります。ただし、「おべんちゃら」はあざとくなってしまうので注意が必要です。思ってもいないお世辞ではなく、本当に思っている褒め言葉を相手に投げかけましょう。
③相手がHSPの場合の対処法③:やわらかなコミュニケーションを心がける
HSPの人は刺激に敏感であるため、辛辣な接し方は控えたほうが無難といえます。穏やかな心地のいいコミュニケーションを心がけましょう。トークスピードを緩やかにしたり、自然な笑顔で接したり、優しい口調で話したりするのが、やわらかなコミュニケーションの手法です。
まとめ
HSPは非常に繊細な人を指し、空気を読み過ぎることで疲れてしまう、刺激に対して敏感になりやすいなどの傾向があります。セルフチェックにすべて当てはまる場合の対処法としては、カウンセリングを受ける、人との距離感を保つなど、さまざまな方法が挙げられます。当記事を参考に、自身に合った方法を試しましょう。
(参考)HSPに関するオススメの本をご紹介
最近では多くのHSP(繊細さん)に関する書籍が出版されています。以下のような書籍は、概要の理解に役立つでしょう。
「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本
今日も明日も「いいこと」がみつかる 「繊細さん」の幸せリスト
仕事、人間関係の悩みがスーッと軽くなる! 「繊細さん」の知恵袋
「敏感すぎて疲れやすい人」がおだやかに暮らしていくための本
- 健康

上級心理カウンセラー、2級ファイナンシャルプランニング技能士
2級ファイナンシャルプランニング技能士の有資格者。長年のライター経験の中で、お金に関する記事を執筆。難しいお金の話しを分かりやすく伝える記事は、読者から読みやすいと好評。