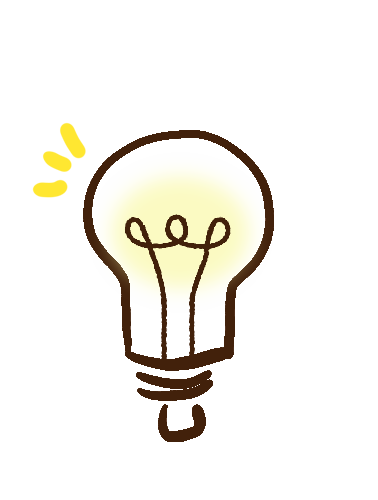夏バテによる疲労回復に おすすめの梅干し! 異国のアレンジ料理3レシピ

暑いです。ただただ暑いです。長かった梅雨が明けたと思ったら、今度は連日の猛暑。そのうえ、今年はマスク着用とあって、自分の吐いた息でさらにまた暑いという…もぅ、たまりませんね。
そんな毎日の8月のテーマは…
本来ならば旬の夏野菜をご紹介したかったのですが、今年は長雨や猛暑で夏野菜が高騰中。
そこで考えました。この記事ではテーマに沿ったレシピを数品ご紹介していますが、せっかくならば食材の金額など気にせず、すぐに試していただきたいと思い、価格は例年と変わらないのに、この時季にとってもおすすめな食材「梅干し」を取り上げます。
目次
梅はその日の難逃れ
昔から薬の役目を担っていた梅干し
今年はマスク着用もあって、熱中症にかかる人が増大。総務省消防局の発表によると、8月17日~23日の 1週間に熱中症で救急搬送された人数は全国で12,799人。前年の同時期は5,566人ですので2倍以上に膨れ上がっています。
熱中症の予防の基本は、適度な水分と塩分の補給。前回は身体にこもった熱をとり、発汗で失われるカリウム補給のための食材【きゅうり】(←前号にリンクを貼ってください)を取り上げましたが、今回ご紹介する梅干しは、発汗で失われる塩分補給にもってこいの食材と言えます。

梅干しは言わずと知れた、昔から馴染みのある梅の加工食品です。梅の歴史を紐解くと、中国から渡ってきたものとか、国内で自生していたものとか諸説あるようです。
梅干しが初めて国内の書物に出てきたのは平安時代。日本最古の医学書『医心方(いしんほう)』に梅干しの効用が取り上げられています。鎌倉時代には縁起物としてもちいられ、戦国時代には武士は梅干しを携帯していたとか。
江戸時代になって、ようやく一般庶民にも広まったと言われています。さらに調べていくと、明治時代にはコレラが大流行。この時に梅干しの薬効や殺菌力が見直されたとか。
「梅はその日の難逃れ」ということわざもあるように、梅干しは私たち日本人にとって梅、昔からお薬のような存在だったようです。【取材協力:和歌山県田辺市梅振興室】
*
さて、毎度恒例の薬膳的解釈をしてみましょう。
梅干しは日本独特の加工食品です。薬膳の本場・中国には梅の加工品で烏梅(うばい)がありますが、これは未成熟な梅の実を燻蒸したものなので、日本の梅干しとは全くの別物。
烏梅は鎮痛や解毒の漢方薬に使われていますが、日本では紅花染の発色剤として使われていて、一部奈良県で生産されているようです。

烏梅については、当コラムの後半にご紹介いたします。
*
気を取り直し、ここでは梅干しを【梅】で解釈します。梅は五性は平性。五味でいえば酸性ですので、収斂(しゅうれん)の性質があります。
したがって、前回の【きゅうり】の時にもご紹介した「肝陽亢盛(かんようこうせい)」の体質の方や、血液ドロドロで高脂血症の方におすすめ。
ですが、気の巡りや血行の悪い「気滞うっ血」の方や、気や血が不足ぎみの「気血両虚」の方、手足が冷たく下痢をしやすいような「陽虚」の方は控えめにしてください。
*
薬膳的効能は「生津止渇(せいしんしかつ)」といって唾液などの分泌を促して、口の乾きを収めたり、肺の機能を回復させて、空咳を止める「斂肺止咳(れんぱいしがい)」。
さらには腸の機能を回復させて、下痢を止める「渋腸止瀉(じゅうちょうししゃ)などが挙げられます。
現代的な考え方からすると、梅にはクエン酸が豊富なので夏バテによる疲労回復や食欲増進、老化防止作用、殺菌効果など。
青梅にはアミグダリンという毒素があるので、生で食べるものではありません。梅干しや梅のシロップ漬け、梅ジャム、梅酒など加工して召し上がってください。
【料理名①】
梅干しでフランスの田舎料理にアレンジ
~梅干しとジャコ入り和風じゃがいものガレット~

材料(2人分)
・じゃがいも(大):2個
・梅干し(大):2個
・ちりめんじゃこ:ひとつかみ
・大葉ジェノヴェーゼ(A):大さじ1
・マヨネーズ:大さじ1
・うすくち醤油:小さじ1
・ブラックペッパー:少々
<A/大葉ジェノヴェーゼの作り方>
・大葉:25枚ぐらい
・ニンニク:1片
・胡桃:5、6個
(※ほかのナッツでも代用可)
・グレープシードオイル:100ml
(※オリーブオイルでも可)
・パルミジャーノ・レッジャーノ:少々
(※ほかの粉チーズでも可)
・天然塩:小さじ1
作り方
1.じゃがいもは皮を剝いて、細切りに。梅干しは種をのぞいてみじん切りにしておく。
2.大葉ジェノヴェーゼは大葉、皮を向いたニンニク、胡桃、グレープシードオイルをミキサーの
中に入れて、パルミジャーノ・レッジャーノを削ったものと塩を入れてスイッチオン。※使わない分は清潔な保存瓶に入れて冷凍しておくと長期保存できる。
3.ボウルに梅干しのみじん切りしたもの、マヨネーズ、うすくち醤油、大葉ジェノヴェーゼ、ジャコを入れて軽く混ぜ、じゃがいもの細切りを加えて全体になじませる。
4.フライパンを中火にかけてオイルをひき、3のじゃがいもを入れて丸く形を整える。
5.5分ぐらいして、フライパンを揺すって固まってきたら裏返しにしてさらに焼く。火が通ったらできあがり。お皿に持って、仕上げにブラックペッパーをふりかけて。
レシピ構築の裏話

このメニューは当コラムのために作ったオリジナルです。発想のヒントは、11年前に出向いた和歌山県の取材からです。
和歌山といえば、梅干しの本場。当時、飲食店の取材もいくつかおこなったのですが、あるお店ではさまざまな料理に梅干しが使われていました。一番印象に残っているのは、ピザに梅干しがトッピングされていたこと。
この時、思ったのです。梅干しだからって和だけのものではない。ジャンルを超えて、塩味としてさまざまな料理に使えるのではないかと。
通常うちでじゃがいものガレットを作る時には、アンチョビを使って塩味とコクを出しているのですが、今回は梅干しの塩味に、ジャコと大葉ジェノヴェーゼでコクを出しました。
これだと蒸し暑い夏場にも、さっぱりと味わえます。ぜひ作ってみられてください!
【料理名②】
梅干しでエスニック料理にアレンジ!
~梅干しの酸味が味の決め手! さっぱり生春巻き~

(写真は1人前)
材料(2人前)
・海老:4尾
・蒸し鶏(裂いたもの):50g
・ゴーヤ(半円型の細切り):8切
・春雨:10g
・レタス:4切
・梅干し:2個
・ライスペーパー:2枚
・スイートチリソース:お好みで!
作り方
1.海老は殻を剝いて背わたを取り、ゴーヤは半円型の薄切りにして軽くボイル。春雨もさっと茹でて戻しておく。※海老とゴーヤ、春雨は一つの鍋で一緒に下処理可。
2.ボイルした海老は薄く半分に切って、梅干しは種を取り、身や皮は細長く切っておく。
3.ライスペーパーを水にくぐらせて、まず手前にレタスをおき、その上に春雨をのせる。一回くるりと巻いて、その先のライスペーパーの上に、海老、梅干しをキレイに並べて左右両端を内側に折る。
4.手前のレタスと春雨のくるまった部分を持って、並べた海老、梅干しの上に巻き込んでくるりと巻いたら、1本できあがり。
5.3~4と同じ要領で、レタス、春雨を包んだ後、今度は海老と梅干かわりに、ゴーヤ、梅干し、蒸し鶏を並べて、左右両端を内側に折り、包み込んだら2本目の生春巻きのできあがり。
レシピ補足
今回は海老、蒸し鶏、ゴーヤを使いましたが、必ずしもこの食材でないといけないわけではありません。梅干しはどんな食材とも相性がいいので、冷蔵庫の中にある食材を代用してもらっても構いません。
料理名③
台湾の夏の定番ドリンクは、
梅サワージュース

酸梅湯(さんめいたん)をご存知でしょうか? 初めて聞いたという方も多いかもしれません。
これは台湾では定番の夏のドリンクで、先にご紹介した烏梅(うばい)をはじめ、漢方薬に使われているいくつかの生薬が入っています。燻した香りと甘みと酸味が絶妙なバランスで、優しく喉を潤してくれます。
つい先日のことです。薬膳の薬効食品を買いに中国食材店に出向いた時、あまりの蒸し暑さに水分を補給したくなりました。そこで、購入したのがコレです。赤い酸梅湯のペットボトル。
口に含んだ瞬間、「あまっ!」。そう甘みがあるのが酸梅湯なのですが、これはあまりにも甘すぎる。そこで自分で作ってみたところ、意外と簡単においしい酸梅湯ができました。
少々アレンジしたオリジナルではありますが、SNSに投稿したところレシピを知りたいという方が数名いらっしゃいましたのでこちらでご紹介いたします。必要な方に届きますように。

材料
・烏梅:10g
・洛神花:5g
・山査子:15g
・陳皮:5g
・甘草:10g
・大棗:6個
・小豆蔲(カルダモン):11個
・ココナッツシュガー:大さじ1
(※粉黒砂糖でも可)
・水:1リットル
以上の生薬は、すべて漢方薬局で購入することができますし、最近では「酸梅湯キット」なるものをネットでお取り寄せすることも可能です。
生薬の分量は好みがあるようで、これといった決まりはないようです。
今回はかなり自分好みに、飲みやすく仕上げました。ちなみに大棗と、小豆蔲を加えたのはオリジナルです。いろいろ調べると、ジャスミン茶や金木犀などを加えてもいいようですよ。
あったかいまま飲んでも構いませんが、キンキンに冷やした方が飲みやすいです。お好みで炭酸水などで割ってもいいかも知れません。
作り方
1. 鍋に水を入れて、生薬をすべて入れて1時間ぐらいおく。
2.強火で沸騰させた後、弱火で20分煮出す。
3.あたたかいうちに、ココナッツシュガーを入れて混ぜ、熱をとる。
(甘みは好みで調整してください)
4.保存のガラス瓶にうつして、冷蔵庫に入れて冷やす。
まとめ
梅干しといっても、日の丸弁当やおにぎりの具材だけにしておくのはもったいない。和え物や煮物以外にも、ガレットや生春巻きなど料理のジャンルを超えて、いろんな風にアレンジできます。
また、この時期の梅干しは夏バテや熱中症予防に加え、疲労回復にも一役買ってくれます。ぜひ梅干しのアレンジ料理を楽しんでみてください。
- 食

ライター・エディター・薬膳料理研究家
独立して26年。拠点は福岡だが、全国誌・地方誌を中心に雑誌、新聞、書籍、企業の印刷物, webを中心にインタビューや取材&執筆を行う。最近では企画から編集、ライティング、キャス ティング、調理、スタイリングを含めたディレクション全般を請け負っている。得意分野は食、健 康、美容等。2013年に薬膳アドバイザー、中医薬膳師の資格を取得。長年、食の取材をしてきた 経験値と、薬膳の知識を融合させたオリジナル薬膳料理教室「薬膳うちごはん」を主宰。
■https:// yakuzenuchigohan.com