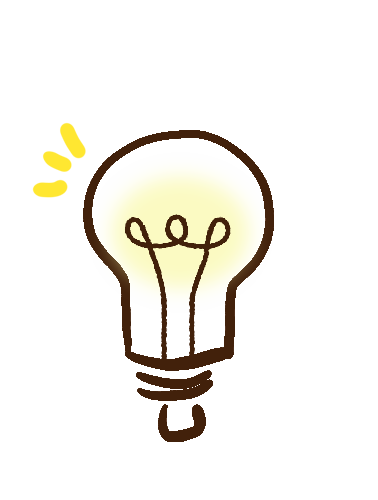身体にこもった熱をとる!優秀な夏野菜・きゅうりレシピ3選で暑気払い

今年ほど梅雨明けが待ち遠しい年はありません。九州は連日の大雨。大きな被害に見舞われているエリアも多々。甚大な被害に遭われた方々、心よりお見舞い申し上げます。
梅雨が明ければ今度は暑い夏がやってきます。今回の記事では、暑さに対処するためにぴったりのきゅうりレシピをご紹介します!
目次
たかがきゅうり、されどきゅうり!暑気払いにもってこいの優秀な食材
ジメジメ、ムシムシ。高温多湿の今時季は不快指数も高め。ちょっと動いただけでも、肌にまとわりつくような、ジトーとした汗をかきます。熱中症にならないようにと意識して水分をせっせと飲んだら飲んだで、翌朝、顔も身体もパンパンにむくむという。なんとも水分摂取のさじ加減がむずかしい季節です。先月ご紹介したとうもろこしレシピも引き続きおすすめですが、今回ご紹介するのはきゅうり。実はこのきゅうり、暑気払い効果の高い優秀な食材なのです。
たかがきゅうりと侮ってはいけません!きゅうりのほとんどは水分で、カリウムを多く含んでいるのが特徴です。
カリウムは体内の余分なナトリウムの排泄を促し、血圧を下げる作用のほか、血液をアルカリ性にする働きもあります。みなさんが懸念する夏バテというのは、実はこのカリウムが汗とともに失われておこる“低カリウム血症”が原因なことが多いとも。そう考えると、カリウムの多いきゅうりこそ、夏バテ予防に最適な食材といっても過言ではありません。
きゅうりを薬膳的観点から解説すると、まずは気を下ろし、身体にこもった熱をとってくれる作用があります。
特に今年はマスクを着用することが多いので、通年以上に気が上がり、身体に熱がこもりがち。かくいう私も先日、炎天下の中、マスクをつけて40分ほど歩いたら、身体に熱がこもり、気が上がって頭がクラクラに。「ヤバい! ついに熱中症になったのか?」と不安になったので、きゅうりをむさぶるようにボリボリかじったところ、熱が引いていくような感覚を覚えました。
※あくまでも食材の特徴を述べたものであり、個人差があります。
体質的に特にきゅうりを食べて欲しい人は、「肝陽亢盛(かんようこうせい)」といって、体格がよくて(肥満ぎみ)、のぼせやすく、イライラして怒りっぽい人です。さらに、きゅうりには尿の出をよくして、身体の余分な水分を排出する「利水効果」もあるので、とうもろこしと同様にむくみ予防にも一役買ってくれます。
ただし、注意点もあります。きゅうりは「寒性」の食材で身体を冷やすため、冷え性の方や胃腸の弱い虚弱体質の方は控えめにお願いいたします。
料理名①:少しのピリリ感と食感が楽しい!〜きゅうりと黒&白きくらげの中華和え〜
材料
2人分の材料です。
・きゅうり…………………………2本
・黒きくらげ………………………1片
・白きくらげ………………………1片
・枸杞(くこ)の実…………….8個
調味料
・ポン酢……………………………大さじ2
・ごま油……………………………大さじ1
・ラー油……………………………小さじ2(お好みで)
・糸唐辛子…………………………少々
・白ごま……………………………ひとつかみ
・塩(板ずり用)..……………ひとつかみ
作り方
- きゅうりを洗ってまな板の上にのせ、塩をふりかけて板ずりする。その後、塩を洗い流しておく(板ずりが面倒な人は飛ばしてもOK!)
- きゅうりはヘタをとって、ピーラーで皮をランダムに向き、一口サイズの乱切りに。
- 黒きくらげと白きくらげは乾燥したものなら、あらかじめ水で戻しておき、生ならそのまま熱湯で1分ほどゆがく。その後、石づきを落とし、黒きくらげは千切りに、白きくらげは食べやすい大きさにちぎっておく。
- ボウルに調味料を合わせて、2のきゅうりと3の黒&白きくらげを入れて和える。
- 器に4をよそって、糸唐辛子をトッピングした後、枸杞の実を添え、白ごまを振りかけたらできあがり。
今回は血液に栄養を与える黒きくらげと、肌を潤したり、免疫力を高める作用がある白きくらげをダブルで入れました。場合によっては黒きくらげだけだったり、白きくらげのみでもおいしく味わえます。ラー油と糸唐辛子による少しの辛味と、きゅうりのみずみずしさとともに味わう、きくらげのコリコリ感が楽しい一品です。
料理名②:小ワザを使ってぐぐっとオシャレに!〜海老&アボカド入りきゅうりのセルクルサラダ〜
(写真は1人分)
材料
2人分の材料です。
・きゅうり…………………………1本
(使用するのはピーラーで薄く帯状にむいた4枚のみ)
・海老……………………………………2尾
・アボカド………………………………1/2個
・しめじ…………………………………6本
・レモン汁………………………………少々
・マヨネーズ…………………………..大さじ2
・チャービル(ハーブ)…………少々
・レッドペッパー(ホール)…6粒
・ブラックペッパー…………………少々
・塩…………………………………………..少々
・オリーブオイル……………………大さじ1
作り方
- きゅうりはしっかり洗った後、ピーラーで薄く帯状にむく。
- 海老は殻、背わたを取って、背から切り込みを入れて半分に。アボカドは皮と種をとり、ひと口サイズにカット。変色防止にレモン汁を少々振る。しめじはほぐしておいて。
- フライパンにオリーブオイルをひいて中火で海老を焼く。半分に切っているので、火が通るとクルクルと巻いた形になる。海老に火が通ったらしめじ、塩を入れて軽く炒めた後、粗熱を取る。
- ボウルに3を入れてマヨネーズで和える。
- 皿の上で1のきゅうりのスライスをくるりと上限に円筒のように型取り、その中に4を入れる。
- 5のトッピングにレッドペッパーを散らし、チャービルを添えたら完成!
レシピ考案時の裏話
とっても優秀な食材なのに、いつも脇役ばかりのきゅうり。どうにかして主役に引き立てられないかと考え、ぐぐっとドレスアップさせた一品です。オシャレでかわいいけれど、まだまだ主役にはなれない現実…。
「きゅうりよ、力不足でごめんなさい!」
と言いながら、この味は特に女性の口に合うと確信しています。美容意識の高い女性のみなさまにぜひ作っていただきたいレシピです!
高温多湿で食欲不振…そんな時は南国・宮崎の郷土料理を!
薬膳は中医学がベース。大まかに説明すると、季節の移り変わりとともに、私たち人間の身体も変化すると考え、個々人の体質に合わせて献立を考えたり、陰陽五行説に沿って季節の食養生を行ったりします。五行説に沿った色体表から今の時季を読み解くと、梅雨に対応する五臓の「脾」は「湿」を嫌います。
つまり、いまの高温多湿によって「脾」の機能が低下すると、胃がもたれたり、疲れやすかったりします。人によってはむくみや下痢といった症状に悩まされる人も。みなさま、心当たりはありませんか? そのままやりすごしていると、そのうち食欲不振に陥り、夏バテへまっしぐらになってしまうかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、宮崎の郷土料理「冷や汁」!
改めて調べると、冷や汁は宮崎だけではなく、昔から全国各地で食べられていたようです。また、鎌倉時代から好んで食べられていたという記述の文献もあり、改めて冷や汁ってすごい! と思った次第。今回、ご紹介する冷や汁はわたくしが取材等でいろんな冷や汁を食べて、一番気に入った鮎を使ったオリジナル冷や汁です。
料理名③:食欲がなくてもスルスル食べられる〜鮎を使った冷や汁〜
材料
2人分の材料です。
・きゅうり………………………………1本
・鮎…………………………………………1尾
・豆腐……..………………………………1/2丁
・みょうが………………………………1個
・大葉…..…………………………………2枚
・ごはん…………………………………1膳
・だし汁(羅臼昆布+鰹)………適量
・白ごま……………………………………少々
・味噌………………………………………少々
作り方
- 鮎に塩を振り、グリルで焼く。その後、身をほぐす。
- だし汁は冷やしておく。
- 野菜はしっかり洗った後、きゅうりは輪切りに。みょうが、大葉は千切りにする。
- フライパンで白ごまを炒り、そこへ味噌加えて焼く。
(この行程はカットしても可。このひと手間で味噌の香ばしさが引き立つ) - すり鉢に4を入れ、冷えただし汁を加えながら味噌を溶かしていく。
- 5の中にほぐした鮎の身と、食べやすく崩した豆腐を加えて混ぜる。
- 器にごはんをよそって、6を加え、輪切りのきゅうり、みょうが、大葉をトッピングしたらできあがり。
私が作る冷や汁には基本的に鮎を使いますが、一般的には鯵やいりこを使うことが多いようです。青魚でも白身魚でもどちらでもいいと考えています。冷や汁は一見、ごはんに冷めた味噌汁をかけて、きゅうりやみょうがなどをのせただけの料理かと思いきや、意外ときちんとしていてそれなりに手間がかかるのです。
しかし、その分おいしさもひとしお。栄養たっぷりの冷や汁は梅雨だけでなく、残暑が厳しい晩夏ぐらいまでのおすすめ料理です。滋味深いお出汁ときゅうりのシャキシャキ感をどうぞお楽しみください。
まとめ
暑さに対処するためにぴったりのきゅうりレシピを3種類ご紹介しました。これらのレシピを参考にしていただき、これからの季節に備えましょう!
【PR】
- レシピ

ライター・エディター・薬膳料理研究家
独立して26年。拠点は福岡だが、全国誌・地方誌を中心に雑誌、新聞、書籍、企業の印刷物, webを中心にインタビューや取材&執筆を行う。最近では企画から編集、ライティング、キャス ティング、調理、スタイリングを含めたディレクション全般を請け負っている。得意分野は食、健 康、美容等。2013年に薬膳アドバイザー、中医薬膳師の資格を取得。長年、食の取材をしてきた 経験値と、薬膳の知識を融合させたオリジナル薬膳料理教室「薬膳うちごはん」を主宰。
■https:// yakuzenuchigohan.com