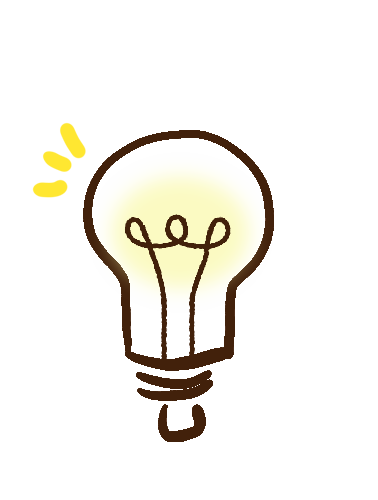ステルス値上げとは?消費者と企業への影響や対策をわかりやすく解説
最近、食品や日用品を買ったとき「以前より量が少ない気がする」「パッケージは変わらないのに中身が減っている」という経験をした人も多いのではないでしょうか。これは「ステルス値上げ」と呼ばれる現象です。本記事ではステルス値上げとは何か、企業側の事情や消費者への影響、対策について詳しく解説します。
ステルス値上げとは?意味や実例を確認

ステルス値上げとは、商品の価格を据え置いたまま内容量を減らす手法です。価格はそのままなので気付きにくいものの、実質的には値上げと同じ効果を持ちます。見つかりにくい値上げという意味で、ステルス値上げと呼ばれます。
ステルス値上げは「シュリンクフレーション」と呼ばれる現象の一種です。縮小という意味の「シュリンク(Shrink)」とモノが値上がりしお金の価値が下がる「インフレーション(Inflation)」を組み合わせた造語で、特に価格据え置きで内容量を減らすケースを指します。
ステルス値上げの代表的なパターン
ステルス値上げとは、主に商品の内容量を変更するものです。それ以外にも、いろいろなパターンのステルス値上げがあります。ステルス値上げの代表的な事例を挙げてみます。
内容量の減少
お菓子1箱あたりの個数や飲料1本あたりの容量が減らされている事例は多くあります。例えば、1箱7個入りのお菓子が6個入りになっているケースや、500mlだったペットボトル飲料が480mlになっているケースです。減らされている量はごくわずかなので、比較しないと気付きにくいのが特徴です。
また、パッケージの見た目の大きさは変えず、容器の底を厚くしたり中敷きを入れるなどの工夫をすることで、内容量が少なくなっていることもあります。
原材料の質の変更
価格や内容量はそのままで、商品の質を低下させるパターンです。例えば、原材料の一部を安価な原材料に切り替えることにより、製造コストは抑えられます。商品の価格が変わらなければ、実質的に値上げになっているといえるでしょう。
サービスの縮小
商品だけでなく、サービスにもステルス値上げはあります。例えば、ホテルなどで無料サービスを削減したり、ポイント還元率を引き下げたりする事例です。
ステルス値上げが行われやすい商品
ステルス値上げの事例が多いのは、以下のような商品です。
ステルス値上げが行われやすい商品
● お菓子(スナック菓子、チョコレート、アイスクリームなど)
● 飲料(清涼飲料水など)
● 日用品(洗剤、トイレットペーパー、ティッシュペーパー)
我々の生活になじみのある商品や日常生活に欠かせない商品で、ステルス値上げが行われています。ステルス値上げが消費者に与えるダメージは大きいと考えられます。
企業がステルス値上げに踏み切る背景とは?

なぜ、ステルス値上げが増えているのでしょうか?企業がステルス値上げに踏み切る背景とは何かを説明します。
原材料費や人件費の高騰
企業がステルス値上げを選択する最大の理由とは、経営環境の悪化です。近年、原材料費の高騰が深刻な問題となっており、小麦、大豆、原油価格の上昇が企業の収益を圧迫しています。特に食品メーカーにとって、これらの原材料費上昇は直接的な打撃となります。
人件費の上昇も企業にとって大きな負担です。最低賃金の引き上げや労働力不足による賃金上昇により、人件費の占める割合は高くなっています。人件費の上昇分をカバーするためには、値上げせざるを得ない状況なのです。
エネルギーコストの増大も見逃せません。電気代やガス代の上昇により、製造コストや店舗運営コストが増加し、企業の利益を圧迫しています。物流コストの上昇も企業を悩ませています。燃料費の高騰やドライバー不足により、配送料が上昇し、企業の負担が増加しています。
消費者心理を考慮した企業戦略
企業がステルス値上げを選択する背景には、消費者心理への配慮があります。価格据え置きにより、消費者は心理的安心感を得やすくなります。消費者は価格上昇に敏感なので、明確な値上げは購買意欲の低下を招く可能性があります。価格を変えなければ、消費者の継続的な購買を促すことが可能です。
競合他社との価格競争も大きな要因です。他社が価格を据え置いている中で、自社だけが値上げを行うと競争力を失う可能性があります。ステルス値上げにより、表面的な価格競争力を維持しながら収益性を確保しているのです。
ブランドイメージの維持という戦略もあります。「お手頃価格」「家計に優しい」といったブランドイメージを持つ企業にとって、明確な値上げはイメージダウンにつながってしまうからです。
値上げの際に企業がとるべき対応
企業が値上げを行う際、とるべき対応とはどのようなことでしょうか?値上げをするにあたって重要なのは、消費者との適切なコミュニケーションです。
企業には、透明性のある情報開示が求められます。内容量変更や品質変更を行う場合、消費者に対してわかりやすく説明することが重要です。パッケージに明記したり、企業ウェブサイトで説明したりすることで、消費者からの信頼を維持できます。
段階的な実施も効果的な手法です。一度に大幅な変更を行うのではなく何回かに分けることで、消費者への影響を最小限に抑えられます。
付加価値の提供により、消費者の理解を得る方法もあります。内容量は減らしても、パッケージの機能性の向上や新しい味の追加などを実施すれば、消費者にメリットを感じてもらえるでしょう。
ステルス値上げが消費者に与える影響とは?

企業がステルス値上げを行った場合に、消費者に対して与える影響はどのようなものがあるのか見てみましょう。
ブランドイメージの低下
ステルス値上げが発覚した場合、企業のブランドイメージに深刻な影響を与えます。消費者は、企業が意図的に情報を隠していたと感じることが多く、ブランドイメージが悪くなってしまいます。一度失われた信頼を回復するには長期間を要するため、企業にとっては大きな損失です。
透明性への疑問も生まれます。消費者は「他にも隠していることがあるのではないか」と疑うようになり、企業の他の商品や取り組みに対しても懐疑的になります。
競合他社への乗り換えを促進する可能性もあります。同じような商品を提供する競合企業がより誠実な対応をしている場合、消費者はそちらに乗り換えるかもしれません。
購買意欲の減退
ステルス値上げの発覚は、消費者の購買意欲を減退させます。「この商品は本当にお得なのか」と疑問を持つようになり、購買に際してより慎重になります。単位価格や内容量をより注意深く確認するようになり、企業同士の競争も激化するでしょう。
値上げが続くと、消費者の節約志向が強くなります。消費者が必需品以外の購買をできるだけ控えるようになれば、企業の売上が減ってしまう可能性もあります。
企業に対する不信感
ステルス値上げにより、その企業に対する不信感が高まるリスクがあります。業界全体への疑念も広がります。一つの企業でステルス値上げが発覚すると、消費者は同業他社に対しても疑いの目を向けるようになるからです。
価格表示への不信も生まれます。表示されている価格や内容量が正確なものなのか、消費者は常に疑問を持つようになります。企業の社会的責任への疑問も感じるようになるでしょう。消費者は企業が消費者の利益を軽視していると感じ、不信感を募らせてしまいます。
消費者ができるステルス値上げ対策

消費者にとって、ステルス値上げも含む物価上昇とは、生活に大きな影響を与えるものです。物価上昇が続いている状況では、今後の対策をしっかり考えておかなければなりません。ここからは、消費者ができるステルス値上げ対策を説明します。
買い物の仕方を見直す
ステルス値上げに対抗する最も基本的な対策は、パッケージの表示を見て買い物をすることです。この場合のパッケージの表示とは、内容量を示すグラム数や個数を意味します。多くのスーパーでは商品の売り場に単位価格が表示されているため、単位価格を見て同じ種類の商品を比較するのもおすすめです。
家計簿をつける
家計簿をつけることは、ステルス値上げ対策だけでなく、支出全体を把握するためにも有効です。家計簿により食費・日用品費の推移を把握すれば、無駄な出費を見直すきっかけになります。家計簿が面倒な人も、スマホの家計簿アプリを利用すればチャレンジしやすいでしょう。
外貨預金や外貨建て資産に投資する
ステルス値上げを含む物価上昇が続くと、インフレになる可能性があります。インフレになると円の価値が下がり、為替相場も円安に動きやすくなります。外貨預金を活用すれば、円安による資産価値の目減りを防げます。外貨建てMMFや外国債券への投資も検討してみましょう。
外貨建て資産への投資には、為替リスクがあります。米ドル、ユーロ、豪ドルなど、安定した通貨へ分散投資すれば、為替リスクを軽減できます。
西日本シティ銀行では、短期間で少額から運用できる外貨預金を扱っています。ぜひ下記からご覧ください。
株式投資を行う
インフレ局面では企業の売上や利益が向上し、株価も上昇する傾向があります。株式投資は有効なインフレ対策の一つです。インフレに強い企業の株を選んで投資しましょう。生活必需品を扱う企業や独占的な技術を持つ企業はインフレ時でも価格転嫁がしやすく、配当金や値上がり益を期待できます。
特定の株を選ぶのが難しい場合は、運用をプロに任せられる投資信託がおすすめです。インデックスファンドのように、市場全体に分散投資する手法もあります。投資にはリスクが伴うため、リスク許容度を考えて無理のない範囲で行いましょう。

まとめ
ステルス値上げとは、パッケージはそのままで商品の内容量を変更するなど、消費者から見えにくい値上げの手法です。企業が直面する課題への対応策の一つですが、消費者としては不信感を抱くことも多いでしょう。物価上昇が続く今、買い物する際の意識を高めるとともに、資産防衛策も考えておくことが大切です。
外貨預金のご留意事項(必ずご確認ください)
商号等:株式会社西日本シティ銀行
投資信託のご留意事項(必ずご確認ください)
商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
■あわせて読みたい
・米の値上げはいつまで続く?高騰の理由と今後について詳しく解説
・2024年に値上げされたものは?高騰の理由と対策をチェックしておこう
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、夫婦カウンセラー
大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。