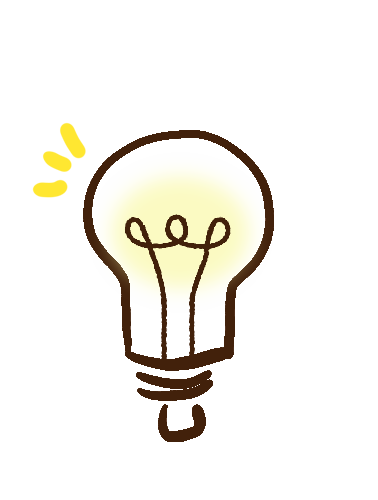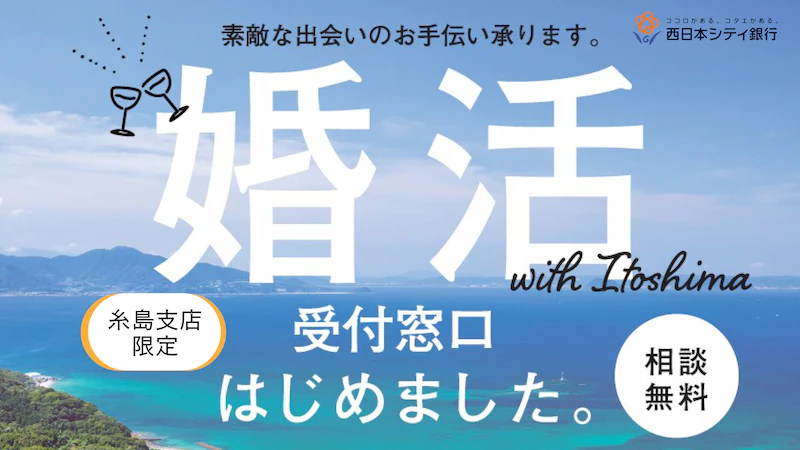「そろそろ結婚したいけれど必要なお金を準備できない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?結婚準備には、結婚助成金を活用できるかもしれません。本記事では結婚助成金をもらえる条件や申請方法、注意点などを解説します。これから結婚準備を始める人は、ぜひ参考にしてください。なお、この記事は、令和6年度の情報に基づいて令和7年1月に執筆したものです。
結婚助成金とは

これから結婚準備を始める人がぜひ知っておきたいのが、結婚助成金の制度です。結婚助成金とは、新婚世帯を経済的に支援するために市区町村から支給される一時金です。結婚新生活支援事業にもとづいて支給されるもので、正式には「結婚新生活支援事業補助金」と言います。
結婚新生活支援事業とは、国から自治体に交付される「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して都道府県及び市区町村が実施している事業です。各自治体が交付金を活用した取り組みを行っているため、結婚助成金の支給の有無や細かい条件も自治体によって異なります。
結婚助成金は毎年こども家庭庁が定める交付要綱にもとづき支給されるため、年度が替わると内容が変更になることがあります。以下、令和6年度の結婚助成金の支給要件や申請方法、注意点について説明します。自治体によっても内容は変わるため、最新の内容はお住まいの市区町村に問い合わせてください。
この記事では、福岡県で結婚助成金に取り組んでいる自治体の中から、4地域それぞれで人口が多い豊前市、朝倉市、直方市、久留米市を取り上げます。
参考元:福岡県庁「福岡県の市町村」
結婚助成金をもらえる条件

結婚助成金は、一定の条件を満たしている世帯が受け取れます。結婚助成金の支給要件をみてみましょう。
参考元:
豊前市「結婚新生活支援事業」
朝倉市「令和6年度朝倉市結婚新生活支援補助金」
直方市「結婚新生活支援補助金(令和6年度)について」
久留米市「久留米市結婚新生活支援補助金」
結婚助成金の対象となる人
結婚助成金の対象となるには、主に次の3つの条件を満たしている必要があります。
結婚助成金の対象となる世帯
- 指定された期間に婚姻届を提出している
- 夫婦の所得の合計が500万円未満(市区町村によっては400万円未満)
- 夫婦とも婚姻日の年齢が39歳以下
結婚助成金をもらうには、市区町村が指定した期間に婚姻届を提出している必要があります。夫婦の所得にも条件がありますが、奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除できます。年齢条件も設けられており、若年層が対象となっています。
市区町村によっては、上記3つ以外の条件が設けられている場合もあります。一般的には、市町村民税の滞納がないこと、一定期間定住の意思があることなどが条件となることが多いです。
結婚助成金の対象となる費用
結婚助成金では、新居の購入・賃貸等にかかる費用と新居への引っ越し費用を支援してもらえます。対象となる費用は次のとおりです。
結婚助成金の対象となる費用
- 新居の購入費
- 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
- 新居のリフォーム費用
- 引越業者や運送業者に支払った費用
結婚助成金の申請期間
結婚助成金を申請できる期間は、各自治体によって定められています。たとえば、令和6年度の結婚助成金の申請期間は、豊前市では令和6年4月1日から令和7年3月31日まで、朝倉市では令和6年4月1日から令和7年3月14日まで、直方市では令和6年6月3日から令和7年3月31日までです。なお、久留米市は予算の上限に達したため、受付が終了しています。久留米市では令和6年6月3日から令和7年2月28日まで、八女市では令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。
結婚新生活支援事業は、市区町村が毎年予算の範囲内で実施しています。申請期間内であっても、予算の上限に達すれば受付終了となります。
結婚助成金はいくらもらえる?

結婚助成金を申請すると、住宅費や引っ越し費用として実際にかかった金額を受け取れます。ただし、次のような上限があります。
結婚助成金の上限
- 夫婦とも29歳以下の世帯…60万円
- 1以外の世帯…30万円
福岡県内でもらえる自治体一覧
福岡県内で令和6年度に結婚新生活支援事業を実施している市町村は次のとおりです。
福岡県内で結婚助成金がもらえる市町村
- 久留米市「久留米市結婚新生活支援補助金」
- 直方市「結婚新生活支援補助金(令和6年度)について」
- 柳川市「新婚世帯マイホーム取得支援事業」
- 八女市「結婚新生活支援事業補助金のお知らせ」
- 筑後市「筑後市結婚新生活家賃支援事業」
- 大川市「大川市結婚新生活支援補助金」
- 豊前市「結婚新生活支援事業」
- うきは市「令和6年度 うきは市結婚新生活支援補助金」
- 嘉麻市「嘉麻市結婚新生活支援事業補助金について」
- 朝倉市「令和6年度朝倉市結婚新生活支援補助金」
- みやま市「新婚世帯への支援(結婚新生活支援事業)」
- 岡垣町「結婚新生活支援補助金」
- 遠賀町「遠賀町結婚新生活支援補助金」
- 小竹町「小竹町結婚新生活支援事業補助金」
- 桂川町「(令和6年6月3日~)桂川町結婚新生活支援事業の申請受付を開始します!」
- 大刀洗町「結婚新生活支援事業」
- 糸田町「結婚新生活支援事業」
- 川崎町「令和6年度結婚新生活支援補助金について」
- 大任町「令和6年度大任町結婚新生活支援補助金」
- 福智町「新婚世帯を応援します!(結婚新生活支援事業補助金)」
- みやこ町「みやこ町結婚新生活支援助成金(令和6年度)について」
- 吉富町「令和6年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について」
- 上毛町「上毛町新婚世帯・子育て世帯新生活応援補助金のお知らせ」
- 東峰村「令和6年度 東峰村結婚新生活支援事業について」
- 芦屋町「新婚世帯の民間賃貸住宅家賃補助制度」
結婚助成金の申請方法

結婚助成金の申請方法や必要書類は自治体によって異なります。申請先の自治体のホームページで申請方法や必要書類を確認しましょう。
ここでは一般的な申請手続きの流れと必要書類を紹介します。
一般的な申請の流れ
結婚助成金は現実にかかった費用を補助してもらう制度です。自治体への申請は、費用を払った後に行います。申請から助成金の受け取りまでは、次のような流れになるのが一般的です。
結婚助成金申請の流れ
1. 必要書類を集める
2. 市区町村の窓口に書類を提出
3. 交付決定通知書が届く
4. 交付請求書を市区町村の窓口に提出
5. 口座に振込がある
申請に必要な書類
結婚助成金を申請する際には、次のような書類が必要になります。
結婚助成金の必要書類
● 補助金交付申請書
● 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
● 世帯全員の住民票の写し
● 夫婦の所得証明書
● 奨学金の返済額を確認できる書類(奨学金返済中の場合)
● 新居に関する書類
補助金交付申請書は、自治体のホームページからダウンロードできる場合が多いです。婚姻を証明する書類として、戸籍謄本や婚姻届受理証明書を用意しておく必要があります。結婚助成金をもらうにはその市区町村に居住していることが条件になるため、住民票も求められます。
新居に関する書類としては、住宅購入の場合には売買契約書や工事請負契約書、賃貸の場合には賃貸契約書などが必要です。実際にお金を払ったことがわかる領収書も提出しなければなりません。
結婚助成金の注意点

結婚助成金を申請するにあたっていくつか注意点があります。「お金をもらえると思っていたのにもらえなかった」ということにならないよう、注意点をよく確認しておきましょう。
どこの自治体でももらえるわけではない
結婚助成金はすべての自治体で実施されている制度ではありません。結婚助成金がもらえるのは一部の市区町村です。居住している市区町村に制度がある場合のみ、申請すればお金をもらえます。
なお、多くの自治体では結婚助成金をもらった後、一定期間居住することが条件になっています。近いうちに転出する予定がある場合には、もらえない可能性があることに注意しましょう。
対象となる費用は限定される
結婚助成金は、結婚準備にかかった費用のすべてを支援してくれるものではありません。結婚助成金の対象となるのは、新居を用意するときにかかった住宅の購入費用や賃貸の初期費用、引っ越し費用に限定されます。結婚式や新婚旅行の費用、家具・家電の購入費用などは支給されません。
結婚助成金として支給される金額には、上限も設けられています。かかった費用の全額をカバーできるとは限りません。
年齢や所得の条件がある
結婚助成金は二人とも39歳以下の夫婦に支給されます。自分が39歳以下でもパートナーが40歳以上の場合、結婚助成金がもらえません。そのため、年齢制限にも注意しておく必要があります。
夫婦の合計所得が500万円未満という要件もあり、収入が多めの世帯はもらえません。夫婦の所得から奨学金の年間返済額を差し引いても500万円以上である場合には、対象外となってしまいます。
なお、結婚助成金をもらえるのは一度のみです。再婚であっても対象にはなりますが、過去に夫婦の一方または双方が結婚助成金をもらったことがある場合には、再びもらうことはできません。
支払いが完了している費用が対象
結婚助成金は、既に支払いが完了している費用が対象です。これからかかる費用については、事前にお金をもらうことはできません。結婚助成金をもらえる場合でも、一旦費用を立て替える必要があります。
なお、結婚助成金の対象となる支払期間も、自治体によって定められています。既に支払いが完了している費用でも、支払ったのが対象期間よりも前であればもらえません。
結婚費用の負担を軽減するには
.jpg?fm=webp)
結婚するにもお金がかかります。結婚助成金は必ずもらえるものではなく、もらえる場合でも結婚助成金でカバーされる費用は一部です。結婚資金が足りそうにない場合、費用の負担を抑える工夫もしましょう。
ここからは、結婚費用の負担を軽減する方法について説明します。
結婚式の内容について見直す
結婚式をすると、まとまった費用がかかってしまいます。費用をかけて結婚式をした方がよいかをよく話し合いましょう。結婚式に特にこだわりがなければ、写真撮影だけをするフォトウエディングにする方法もあります。
結婚式をする場合でも、費用を抑えられるポイントはいろいろあります。例えば、招待客を親族や親しい友人のみにしたり、招待状や席次表などのペーパーアイテムを手作りしたりするなど、さまざまな視点で費用を抑える手段を考えてみましょう。
父母・祖父母から非課税贈与を受ける
結婚費用を父母や祖父母から援助してもらう方法もあります。父母や祖父母から結婚・子育て資金の贈与を受ける場合、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という特例が利用できます。結婚資金については300万円まで、子育て資金と合わせて1,000万円まで非課税の扱いが受けられます。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を受けるには、銀行に専用口座を開設し、贈与を受けたお金を一括して預入しましょう。結婚費用に使った領収書を銀行に提出すれば、資金を引き出すことができます。
特例を利用して非課税贈与を受ければ、父母や祖父母にとっても相続税対策になることがあります。父母や祖父母が結婚費用を出してくれそうな場合には、ありがたく受け取ることも検討しましょう。
>>西日本シティ銀行で結婚・子育て資金贈与の口座を作るなら?
ローンを活用
ローンを利用するのも一つの方法です。結婚式の費用に関しては、結婚式場が提携しているブライダルローンを申し込める場合が多いでしょう。ブライダルローンを取り扱っている銀行もあるため、銀行で申し込む方法もあります。
ブライダルローンの資金使途は主に挙式や披露宴の費用で、住宅費や新居への引っ越し費用などには使えないことが多くなっています。幅広い目的で使いたい場合には、カードローンやフリーローンを検討してみるのがおすすめです。
フリーローンやカードローンは、銀行で申し込みができます。フリーローンは申し込み時に使途を申告し、必要な資金を一括して借入するローンです。カードローンでは使途の申告不要で、利用限度額の範囲内で何度でも借入ができます。金利や返済期間なども考え、自分に合ったローンを選びましょう。
>>結婚資金に便利なローンについて(NCB EZ多目的ローン)
>>アプリで申し込み完結したいなら、NCBアプリ カードローン
まとめ
結婚助成金を活用すれば、十分な貯金がなくても結婚生活をスタートできる可能性があります。近い将来結婚を考えている人は、結婚助成金をもらえる条件や注意点を確認してみるのがおすすめです。結婚助成金を利用できない場合には、親からの贈与やローンの活用も検討してみましょう。
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、夫婦カウンセラー
大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。