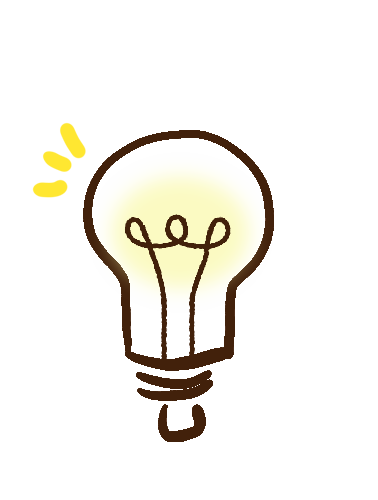【2025年】iDeCo改正で何が変わる?運用のメリットやデメリットを詳しく解説
将来への備えとして注目されるiDeCoが、制度改正により拡充されます。2024年12月には一部改正が行われ、さらに2025年の税制改正大綱でも掛金上限額の引き上げや加入可能年齢の拡大などが予定されています。本記事では、2024年・2025年のiDeCo制度改正のポイントと、運用におけるメリット・デメリットを詳しく解説します。※2025年5月27日現在の情報です。
目次
そもそもiDeCoとは
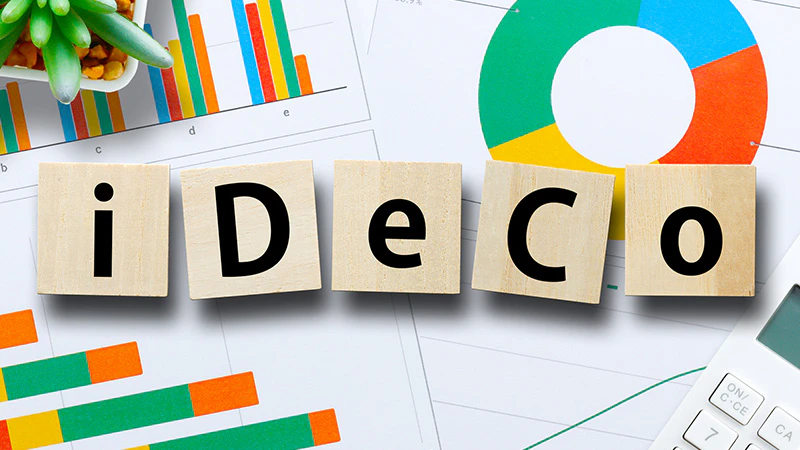
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、老後資金を準備するための私的年金制度の一つです。毎月拠出した掛金を自分で運用しながら資産を形成し、60歳以降に年金や一時金で受け取る仕組みです。
iDeCoには、税制優遇を受けながら資産運用ができるメリットがあります。iDeCoの税制優遇とは、次の3つです。
iDeCoの税制優遇
- 掛金が全額所得控除の対象
- 運用益が非課税
- 資産受取時も控除の適用あり
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、所得控除の一つである「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。掛金の全額が控除の対象となるため、所得税・住民税の節税効果が大きくなっています。
iDeCoでは、運用中に得られる利益(利息・配当・値上がり益)には税金がかかりません。通常の投資であれば約20.315%の税金が課されますが、iDeCoではこれが非課税になるため、その分、資産形成に有利です。ただし、資産の受け取り時には課税される可能性がある点には注意が必要です。
【2024年12月改正】iDeCoはどう変わった?

国は老後資金の自助努力を促すため、iDeCo制度を段階的に見直しています。2024年12月に実施された改正では、次のような変更が行われました。
会社員・公務員の掛金上限額が変更
iDeCoで拠出できる掛金の月額には、上限が設けられています。掛金上限額は、国民年金の被保険者種別などによって異なります。これまで、第2号被保険者のうち公務員及び勤務先にDB(確定給付企業年金)のある人の掛金上限額は月1.2万円でしたが、改正により月2万円に引き上げられました。
なお、企業年金に加入している場合は、iDeCoの掛金と企業年金の掛金の合計額の上限が月5.5万円という制限もあります。そのため、5.5万円から企業年金の掛金を引いた額が2万円よりも少ない場合には、その金額がiDeCoの掛金上限額となります。企業年金の掛金額によっては、iDeCoの掛金上限額が2万円よりも少なくなる (企業年金の掛金を差し引いた残りの額となる)場合があります。
iDeCo加入時の勤務先への申請が不要に
以前は会社員・公務員がiDeCoに加入する場合、勤め先から事業主証明書をもらい、提出する必要がありました。改正により、事業主証明書の提出は不要となりました。これにより、会社員・公務員も自分の意思でスムーズにiDeCoに加入できるようになっています。
【2025年税制改正大綱】iDeCoは今後さらに拡充する見込み

2024年12月に閣議決定した2025年の税制改正大綱にも、iDeCoの改正について盛り込まれています。今後改正される主な点は以下のとおりです。
改正点①掛金上限額の引き上げ
2024年の改正でも第2号被保険者の一部の掛金上限額が引き上げられましたが、今後はさらに幅広い引き上げが予定されています。第1号被保険者は現行の月6.8万円から月7.5万円となり、第2号被保険者のうち企業年金がない人は月6.2万円となる予定です。企業年金がある場合は、企業年金とiDeCoの合計で月6.2万円が上限となります。
改正点②70歳未満なら加入可能に
現行制度では、iDeCoの加入可能年齢は65歳未満に制限されています。ただし、iDeCoに加入するには、国民年金被保険者である必要があります。60歳以上では以下に該当する人のみが国民年金被保険者となり、iDeCoに加入できます。
60歳以上でiDeCoに加入できる人
- 国民年金に任意加入している人
- 厚生年金に加入して働いている会社員・公務員
今後の制度改正により、国民年金被保険者であれば70歳に到達するまでiDeCoに加入できるようになる見込みです。また、次に当てはまる人は70歳までiDeCoに加入できるようになります(既に老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っている人は対象外)。
60歳以上70歳未満で新たにiDeCoに加入できる人
- iDeCoの加入者・運用指図者だった人
- 企業年金等の資産をiDeCoに移管できる人
改正点③マッチング拠出が制限なしに
企業型DC(企業型確定拠出年金)では企業(事業主)が従業員に代わって掛金を拠出します。ただし、従業員自らも上乗せして掛金を拠出できる「マッチング拠出」の制度を採用している企業もあります。
現行制度では、マッチング拠出の金額は事業主掛金を超えてはならないという制限があります。しかし、今後の改正で、マッチング拠出の掛金額の制限が撤廃される予定です。従業員が事業主掛金よりも多くを拠出することも可能になり、より柔軟かつ積極的な資産形成ができるようになります。
改正点④企業型確定拠出年金の掛金上限額も変更
企業型DCの掛金額の上限も引き上げられます。現行制度ではiDeCoと企業型DCの掛金の合計は月5.5万円までですが、この上限が月6.2万円に引き上げられます。iDeCoの掛金額の月2万円という上限は撤廃されるため、6.2万円から企業型DCの掛金額を差し引いた金額までiDeCoに拠出できます。
iDeCo改正によるメリットとデメリット
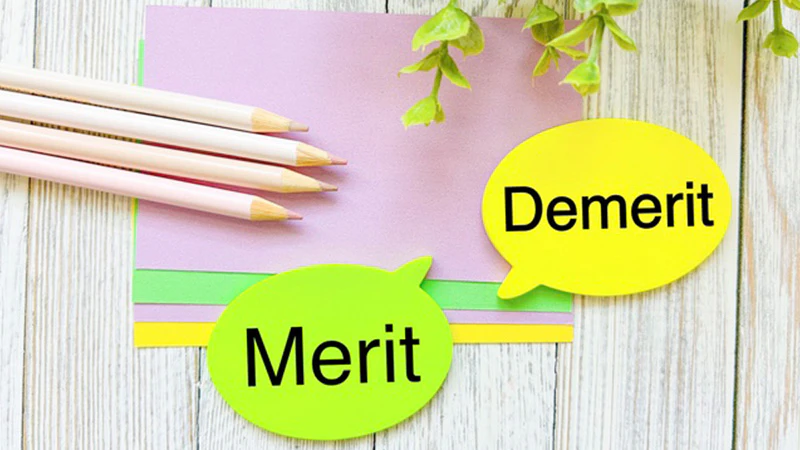
制度改正によりiDeCoの利便性や柔軟性は向上しますが、一方で注意点もあります。iDeCo改正によるメリット、デメリットを把握しておきましょう。
【メリット】節税しながらより効果的な資産形成が実現
iDeCoの最大のメリットは、税制優遇を受けながら老後資金を積み立てられる点です。iDeCoには税金が抑えられる分、資産を効率よく増やす効果があります。制度改正によって、より効率的に老後資金を準備できるようになります。
毎月拠出できる掛金額が増えることで、より多くの資金を非課税で運用できます。利益が利益を生む複利効果により、資産をより増やせる可能性があります。加入可能年齢の引き上げにより、運用期間をより長く確保できるようになります。長期的な運用が可能になれば、リスクを抑えながら着実な資産形成ができます。
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象となるため、iDeCoに加入している期間は所得税・住民税が軽減されます。iDeCoに加入できる期間が長くなれば、節税できる期間も長くなるのもメリットです。
【デメリット】受給のタイミングにより税負担が増えるかも
iDeCoで積み立てた資産は、一時金または年金で受け取ることができます。一時金として受け取る場合は退職所得控除、年金として受け取る場合は公的年金等控除の対象となり、それぞれ税負担が軽減される仕組みです。ただし、受け取り方によって、税金の負担が増える可能性があります。
特に注意したいのは、一時金で受け取る場合です。iDeCoの一時金と退職金の受け取りが同時期になる場合、退職所得控除の枠を大幅に超えてしまうことがあります。iDeCoの掛金を増やして受け取れる資産が増えたとしても、税負担が増加すれば、iDeCoの節税メリットが相殺されてしまうおそれがあります。
参考:国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
iDeCo改正による今後の選択肢

iDeCoの制度改正により、個人の選択肢も広がります。自分に最適な活用法を見つけるために、以下の点を見直してみましょう。
iDeCo改正で自分がどう変わるのかをチェック
iDeCo改正により、月々に拠出できる掛金の上限が変わる人が多くなっています。2025年現在の掛金上限額と、今後の改正による掛金上限額は次のとおりです。
| 2025年現在の掛金上限額 | 今後の改正による掛金上限額 |
|---|---|---|
第1号被保険者 自営業者・フリーランス等 | 月6.8万円 | 月7.5万円 |
第2号被保険者 企業年金なしの会社員 | 月2.3万円 | 月6.2万円 |
第2号被保険者 企業年金ありの会社員 | 月2万円 | 月6.2万円(企業年金と合算) |
第2号被保険者 公務員 | 月2万円 | 月6.2万円(退職等年金給付と合算) |
第3号被保険者 専業主婦等 | 月2.3万円 | 月2.3万円 |
第3号被保険者以外の人は、iDeCo改正により掛金上限額が変わります。企業年金がある会社員及び公務員については、iDeCo単独の固定的な上限額という考え方がなくなり、企業年金等と合わせた拠出限度額の範囲内でより柔軟にiDeCoの掛金を設定できるようになります。
今後はiDeCoの加入可能年齢が70歳未満に引き上げられます。ただし、次の人はiDeCoに加入できません。
加入年齢が引き上げられてもiDeCoに加入できない人
- 老齢基礎年金を受給している人
- iDeCoの老齢給付金を受け取っている人
老齢基礎年金の受給開始は原則65歳からです。繰下げ受給を選択すれば、iDeCoに70歳まで加入して掛金を拠出することも可能になります。
掛金や金融機関を変更する方法
iDeCoに加入している間に、掛金の金額や金融機関を変更することは可能です。掛金上限額の引き上げにより、毎月の掛金額の見直しや他の金融機関への乗り換えをしたいという人も多いでしょう。そこで、iDeCoの掛金や金融機関を変更する方法を説明します。
iDeCoの掛金額の変更
iDeCoの掛金額は年に1回(12月分から翌年11月分までのうちに1回)変更ができます。掛金額を変更する場合、加入先の金融機関から「加入者掛金額変更届」を入手し、必要事項を記入して提出します。提出日によって何月から変更になるかが変わるため、事前に加入先金融機関で確認しておきましょう。
iDeCoの金融機関の変更
iDeCoの金融機関(運営管理機関)を変更する場合、変更先の金融機関に資産を移す必要があります。手続きは変更先金融機関で行います。変更先金融機関で「加入者等運営管理機関変更届」等の書類を入手し、必要書類を提出して手続きしましょう。
まとめ
2024年12月のiDeCo改正により、一部の会社員・公務員の掛金上限額が増額され、加入手続きも簡素化されました。2025年の税制改正大綱でも、掛金上限額のさらなる引き上げや加入可能年齢の拡大など、iDeCoの拡充が予定されています。老後資金に不安を感じている方は、iDeCoの活用を検討してみるとよいでしょう。
>>西日本シティ銀行 iDeCo(個人型確定拠出年金)についてはこちらをご覧ください。

投資信託のご留意事項(必ずご確認ください)
商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
■あわせて読みたい記事
・【福岡のFPさんコラム】家計管理の迷子になっていませんか?FPからの家計改善のアドバイス
・NISAとiDeCoの賢い活用法|上手に使い分けるためにもライフプランを作成しましょう!
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、夫婦カウンセラー
大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。