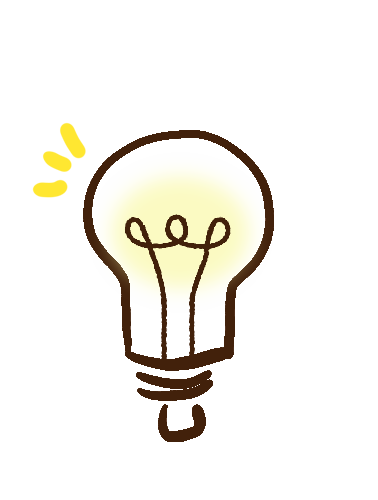NISAと投資信託の違いは?それぞれのメリットとデメリットを理解しよう
NISAや投資信託に興味はあるものの、投資経験がないので不安という人も少なくないでしょう。この記事では、NISAと投資信託の違いやメリット・デメリットを解説し、注意点などをまとめました。これから資産運用をスタートする際の参考にしてみてください。
投資信託とNISAの違いは?
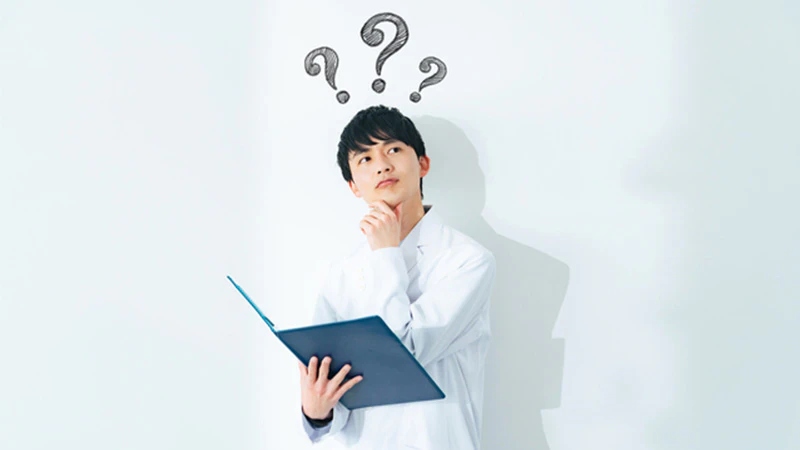
投資信託やNISAはよく耳にする言葉ですが、それぞれの意味を正しく理解することが大切です。混同しないようにそれぞれの特徴を確認しましょう。
投資信託とは
投資信託(ファンド) とは、投資家から集めた資金をプロが運用し、その成果を投資家に分配する仕組みの金融商品のことです。投資対象は国内外の株式や債券、不動産投資信託(REIT)など多岐にわたります。
投資信託にはさまざまな種類の商品があり、投資家はどのような銘柄で構成されているかを目論見書で確認できます。運用のプロが投資家に代わって目論見書の内容で投資するため、個人で銘柄を選ばずに分散投資が可能なのが特徴です。
NISA(少額投資非課税制度)とは
NISA(少額投資非課税制度)とは、金融商品の運用で得られた利益が毎年一定額まで非課税になる制度のことをいいます。
投資信託は金融商品であるのに対して、NISAは投資の利益を非課税にできる制度のことを指します。そのため、NISAという枠組みを利用して投資信託を運用するのも可能です。
通常、投資による運用益は約20%課税されますが、NISAを利用することで一定額までが非課税になります。さらに、非課税になる期間は無期限です。こうした高い節税効果がNISAが注目される理由の一つとなっています。
投資信託とNISAの違いを比較
投資信託とNISAの違いを比較表にしました。NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があります。対象投資商品や年間投資枠に違いがあります。併用可能ですので、目的に合わせて選ぶのがおすすめです。
投資信託 | NISA | ||
|---|---|---|---|
内容 | 【投資商品】 | 【投資の制度】 | |
投資枠 | ー | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
対象年齢 | 原則18歳以上※ 未成年口座の開設可能(ただし親権者の同意書・親権者名義の口座開設が必要) | 18歳以上 | 18歳以上 |
税率 | 運用益の20.315% | 非課税 | 非課税 |
年間非課税枠 | ー | 120万円 | 240万円 |
非課税保有限度額(総枠) | ー | 1,800万円 | |
非課税期間 | ー | 無制限 | 無制限 |
対象投資商品 | 国内外の株式・債券・リートなど | 国内外を投資先とする金融庁指定のインデックス投信310本(2025年2月15日現在) | 上場株式・投資信託・ETF・リートなど(整理・監理銘柄や毎月分配型の投資信託、信託期間20年未満、高レバレッジ型のものは除外) |
買付方法 | 積立・一括 | 積立のみ | 積立・一括 |
最低投資金額 | 金融機関により異なる(100円~1万円) | 金融機関により異なる(ネット証券は100円~、銀行・証券窓口は1,000円~) | 同左 |
途中引き出し | 自由 | 自由 | 自由 |
※未成年者の口座開設は金融機関により取扱い条件が異なる
投資信託の特徴

資産運用の一つの選択肢として初心者にもおすすめできる投資信託ですが、注意しなければならない点もあります。メリット・デメリットの両方を理解したうえで、投資信託を始めるようにしてください。
投資信託のメリット
投資信託の主なメリットとして挙げられるのは、以下の3つです。これらは、投資初心者におすすめの理由にもなっています。
少額から投資できる
投資はまとまった資金が必要だと思われがちですが、投資信託は少額から始められるのが特徴 です。金融機関によっては100円から購入可能なケースもあり、初心者でも無理なく投資を始められます。
最初は少額からスタートし、慣れてきたら金額を増やしていくことで、リスクを抑えながら投資に挑戦できます。
分散投資でリスク軽減
投資信託は複数の株式や債券、不動産などに分散投資できるため、リスクを抑えやすいのが特徴です。
分散投資は、投資リスクを抑える方法の一つです。投資信託は株式や債券、不動産などのさまざまな商品が選択でき、値動きの異なる複数の投資先を組み合わせることで大きな損失を抑えられます。
仮に、株式のみの投資信託であっても、複数の企業の株式が組み入れられているため、個別株よりも値動きのリスクを分散できます。意識せず分散投資できるのも、投資信託のメリットといえます。
プロに運用を任せられる
投資信託の運用は投資の専門家が行うため、知識や経験がなくても始めやすいという特徴があります。
通常の株式投資では、銘柄選びや売買のタイミング、投入金額などを全て自分で判断しなければなりません。投資信託の場合、プロに任せられるため手間が不要でリスクを低くできるのです。
ただし、プロが運用するからといって必ず利益が出るわけではなく、市場環境によっては損失が発生することもあります。
投資信託のデメリット
投資信託を始める際に特に注意したいのは、以下の2点です。デメリットがあることも理解しておきましょう。
預金と違い元本保証がない
投資信託は、銀行預金とは異なり元本保証がありません。市場の動向により、購入時よりも基準価額が下がる可能性があり、元本割れのリスクも伴います。
投資信託に組み入れられる株式や債券は、国内外の政治・経済情勢や市場環境により価格が変動します。そのため、売却価格はタイミングによって購入価格よりも下回ることがあるのです。
運用コストがかかる
投資信託は専門家に運用を任せると説明しましたが、そこには手数料が発生します。具体的には運用管理費用(信託報酬)、購入時手数料、信託財産留保額(途中解約時費用)の3つです。
ただし、最近は低コストのインデックスファンドや、購入時手数料がかからない「ノーロード型」の投資信託も増えているため、コストを抑える選択肢もあります。投資信託を選ぶ際には、手数料がどの程度かかるのかを確認することが重要です。
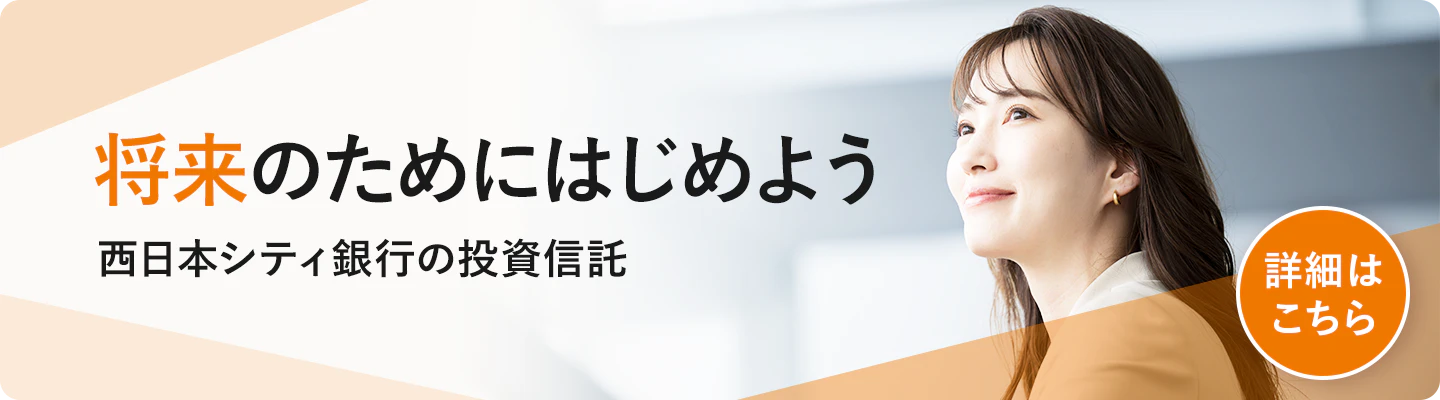
NISAの特徴

通常の投資と違いNISAは大きな節税効果が期待できますが、NISAならではの特徴や注意点も理解しておくことが必要です。ここではメリットとデメリットの両方について解説します。
NISAのメリット
課税口座で運用するのと比べ、NISAを利用することで得られるメリットを以下に紹介します。
運用益が無期限で非課税
配当金や売却益などの運用益が無期限で非課税になるのは、NISAの大きなメリットの一つです。2024年1月からNISA制度が新しくなり、非課税保有限度額(総枠)が最大1,800万円になったことで注目が集まりました。
NISAには成長投資枠とつみたて投資枠の2種類があります。成長投資枠は年間240万円、つみたて投資枠は年間120万円がNISAにおける年間投資額の上限額で、株式や投資信託など運用したい商品を選べるのもNISAの特徴です。
柔軟な運用が可能
NISAは少額から投資できるだけでなく、いつでも売却可能な柔軟性もあります。
特に2024年からの新NISA制度では、売却した分の枠が翌年以降に再利用可能となりました。これにより、ライフプランに応じた資産運用がしやすくなります。
確定申告の必要がない
NISAは運用益が非課税となる制度のため、確定申告をする必要はありません。一般口座や特定口座のような課税口座で運用する場合は運用益に対して約20%課税されますが、NISAは非課税なのでそのまま運用益を受け取れます。確定申告は慣れないと手続きが面倒ですが、NISAではその手間が省けるため、投資初心者でも安心して利用できます。
NISAのデメリット
非課税で柔軟な運用ができるNISAには、注意すべき点もあります。以下の2つのデメリットもしっかり押さえておきましょう。
選べる商品が限られている
NISAはどのような商品も購入できるわけではありません。つみたて投資枠は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託とされ、金融庁の基準を満たす投資商品のみが対象です。
成長投資枠は投資信託や上場株式などが対象で、つみたて投資枠よりも対象商品の範囲は広いですが、一部除外もあります。投資に慣れていて自由に商品を選びたい人にとっては少し物足りなさを感じる部分です。
損益通算や繰越控除ができない
NISAは運用益が非課税になる反面、損失が出た場合の税優遇措置が受けられません。
特定口座など複数の課税口座での運用で売却時に損失が出た場合は、その他の売却益や配当金と損益通算が可能です。これに対し、NISAでは非課税という恩恵がある代わりに、損益通算のような税負担を軽くする措置がありません。
さらに、損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺する「繰越控除」も適用されません。損益通算や繰越控除を活用して税負担を軽減したい場合は、課税口座での運用も併用するのがおすすめです。

NISAで投資信託を始める際のポイント

NISAを活用した投資信託は投資初心者でも始めやすく、節税や分散投資できるなどのメリットもあります。ここでは、上手に活用するための心構えやポイントをまとめたので、参考にしてみてください。
目的を明確にする
資産形成を始める際は、何のために行うのかを明確にしておくことが重要です。目的に応じて必要な金額や期間を決めることにより、商品選びや運用の方向性が見えてくるからです。
子どもの教育資金を確保する、老後の生活に備えるなどライフイベントに合わせて資産形成プランを立てることが大切です。そのうえで、NISAのつみたて投資枠と成長投資枠のバランスを考えた商品選びをするのが迷わないコツです。
長期的な視点で運用
NISAを利用した投資信託は、長期運用をおすすめします。NISAの運用益は非課税で期間も無制限のため、短期間で利益を狙うよりも、じっくり時間をかけて資産を増やす方が効果的なためです。特につみたて投資枠を活用する場合、短期的な値動きを気にするのではなく、長期的な視点で積立を続けることが大切です。
また、長期運用では分散投資が基本です。投資信託自体が分散投資の仕組みを持っていますが、さらに株式や債券など異なる資産を組み合わせることで、リスクを抑えながら安定した運用を目指すことができます。
わからないときは相談
投資信託やNISAについて理解したつもりでも、いざ始めてみるとわからないことも出てくるでしょう。その際は、NISAを取り扱っている金融機関に相談するのがおすすめです。
証券会社や銀行などの公式サイトでは、わざわざ出向かなくてもチャットサポートを受けられるところもあります。また、運用方針などをじっくり対面で相談したい場合は、窓口に足を運んで話を聞くことも可能です。
>>お気軽にご相談ください。西日本シティ銀行ではインターネットでご来店予約もできます。
まとめ
物価高騰が続く中、預金や貯金だけでは資産価値が目減りする可能性があります。対策として節約や投資が考えられますが、その選択肢の一つとしてNISAを活用した投資信託は有効です。投資には慣れていないが将来に向けた資産形成をしたいという人は、まず少額スタートから検討してみてください。
投資信託のご留意事項(必ずご確認ください)
商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
■あわせて読みたい記事
・【初心者必見】投資信託の始め方ガイド!対象の種類や運用方法、気をつけるポイント
・100万円を運用!投資信託や他の運用方法の中から初心者にもおすすめの3つを紹介
・NISAとiDeCoの賢い活用法|上手に使い分けるためにもライフプランを作成しましょう!
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学卒業後、システムエンジニアを経て通信機器商社の経営戦略室で新規事業の立ち上げに参画。退社後はシステム会社の代表取締役に就任し、パソコン通信サービスを展開。1996年に著書『わかる!イントラネット』執筆後はフリーランスとして活動。事業経験とFP資格を活かしビジネス系ライターとして複数メディアで執筆中。