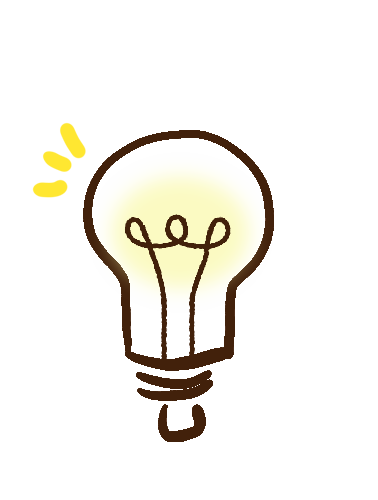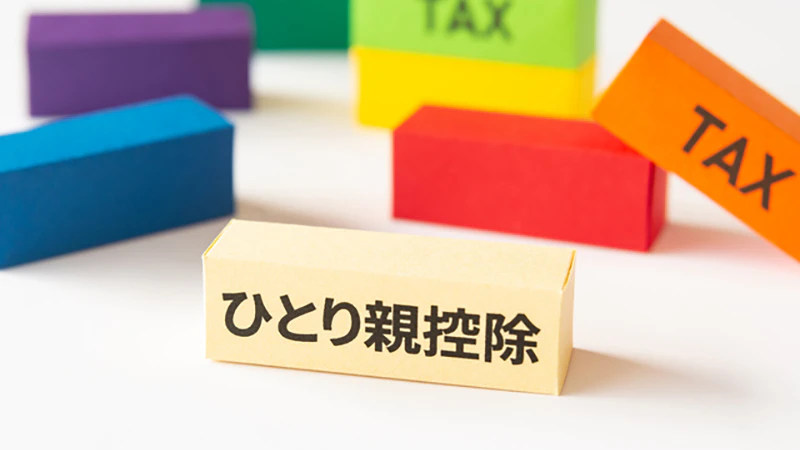子どもの教育費はどう準備する?貯金の仕組みと親ができるサポートのコツ
子どもが成長するにつれて必要となる教育費は、家庭にとって大きな負担です。大学進学時にはまとまった資金も必要になるため、早めの準備が必要です。本記事では、子どもの教育費を準備する具体的な方法や、親ができるサポートのコツをわかりやすく解説します。
目次
子どもの教育費の現状と貯金の重要性

子どもを育てるのにはお金がかかりますが、特に負担が大きいのが教育費です。まずは、子どもの教育費はどれくらいかかるのか、目安を知っておきましょう。
幼稚園から高校までにかかる教育費
文部科学省が行った「令和5年度 子供の学習費調査」によると、幼稚園から高校まで年間にかかる学習費総額は次のとおりです。
幼稚園から高校までの学習費総額
| 公立 | 私立 |
|---|---|---|
幼稚園 | 18万4,646円 | 34万7,338円 |
小学校 | 33万6,265円 | 182万8,112円 |
中学校 | 54万2,475円 | 156万359円 |
高等学校(全日制) | 59万7,752円 | 103万283円 |
「学習費総額」とは、学校教育費、学校給食費、学校外活動費の合計です。高校の授業料については、所得に応じて支援される「高等学校等就学支援金制度」がありますが、学校教育費は本制度適用後の実際に支出した金額を指します。
子どもが高校までにかかる費用は、公立と私立で大きく変わります。公立の場合、最も費用がかかるのは高校在学中ですが、年間約60万円です。一方、私立の小学校、中学校、高校ではいずれも年間100万円以上かかります。1か月あたり約8万~15万円の負担となります。
大学に進学する場合にはまとまったお金がかかる
子どもが大学に進学する場合には、まとまった教育費が必要です。大学の入学金と年間授業料の目安は次の表のとおりです。
※国公立大学は省令で定められた金額、私立大学は平均額
大学の入学金及び年間授業料
| 入学金 | 授業料 | 施設設備費 |
|---|---|---|---|
国公立 | 28万2,000円 | 53万5,800円 | なし |
私立(文科系) | 22万3,867円 | 82万7,135円 | 14万3,838円 |
私立(理科系) | 23万4,756円 | 116万2,738円 | 13万2,956円 |
私立(医歯系) | 107万7,425円 | 286万3,713円 | 88万566円 |
私立(その他) | 25万1,164円 | 97万7,635円 | 23万1,743円 |
出典:国公立大学等の授業料その他の費用に関する省令
出典:文部科学省「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等 平均額の調査結果について」
大学の入学金や授業料は高額です。私立では施設設備費も発生するため、文系でも年間100万円以上かかることがあります。医歯系学部の場合には6年間在学するため、私立に進学すると2,000万円を超える学費となります。
上記はあくまで大学に納付するお金です。大学在学中には、教科書代や通学の交通費などもかかります。子どもが遠方の大学に進学する場合には、下宿代も必要になります。
子どもの教育費を毎月の生活費から出すのは困難
子どもが高校までは、公立なら毎月の家計から教育費を賄えるかもしれません。しかし、大学に進学するとなると、簡単にはいかなくなります。短大や専門学校に進学する場合も同様です。
子どもの進学費用は、必要になる時期がわかっています。まとまった金額になりますが、将来に向けて計画的に準備ができます。将来子どもに進学を諦めさせることのないよう、必要な金額の目安を知って、貯蓄をしておきましょう。
以下、子どもの教育費を貯蓄するためにどんな方法があるかを解説します。
教育費を貯蓄する方法①「預貯金で積み立て」

子どもの教育費を準備する最も身近で基本的な方法の一つが、銀行などの預貯金でコツコツと積み立てる方法です。
預貯金で積み立てて教育費を準備する方法とは
教育費を預貯金で積み立てる場合には、積み立て専用の預貯金専用口座を作るのが基本です。毎月貯蓄に回す金額を専用の普通預金口座に移す方法もありますが、おすすめは自動積立定期預金を利用する方法です。
自動積立定期預金を利用すれば、毎月指定した額を普通預金口座から引き落とし、自動的に積み立て専用の定期預金口座に移してもらえます。引き落とし日を給料日直後にしておけば、先取りで確実に貯蓄できます。
西日本シティ銀行では、教育費の貯蓄に役に立つ預金商品やその他のサービスを用意しています。早い時期から計画的に教育費を貯蓄する際は、ぜひご活用ください。
教育費を預貯金で準備するメリット
預貯金の大きな魅力は、安全性と利便性です。元本が保証されているため安心して積み立てができ、必要なときにはすぐに引き出せます。少額から始められるため、誰でも気軽に教育費準備をスタートできる点もメリットです。
教育費を預貯金で準備するデメリット
現在の金利は上昇傾向にあるとはいえ、決して高い水準ではないため、預貯金では利息が付いても大きくは増えません。インフレが進めば、実質的に資産価値が目減りする恐れもあります。生活費と混ざって流用してしまう可能性もあるため、教育費専用口座を設けるなどの工夫が欠かせません。
教育費を貯蓄する方法②「学資保険などの保険を利用」
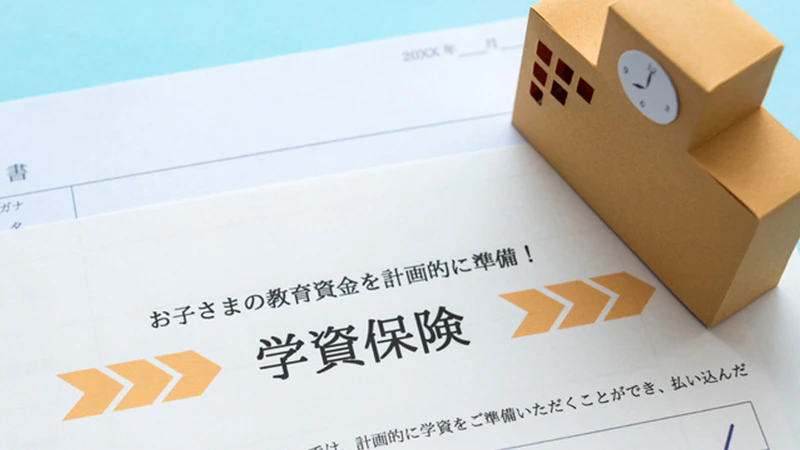
学資保険や終身保険を利用して子どもの教育費を準備することも可能です。
保険を利用して教育費を準備する方法とは
学資保険は、子どもの教育資金の確保を目的とした貯蓄型の保険です。契約者(親)が保険料を一定期間払い込み、進学のタイミングに合わせてお祝い金や満期保険金を受け取ります。契約者に万一のことがあった場合、保険料の払い込みは免除されますが、お祝い金・満期保険金は予定通り受け取れます。
終身保険は保障が一生涯続く生命保険です。途中で解約すると、解約返戻金を受け取れます。保険料を払い込んでおけば、教育費が必要な時期に解約返戻金を受け取れるため、貯蓄としても使えます。
>>お子さま連れも安心して来店・相談できる「NCBほけんプラザ」
教育費を保険で準備するメリット
保険を利用する場合、毎月の保険料を自動的に積み立てられるため、確実に貯蓄ができます。親に万一のことがあった場合には保険料が免除され、子どもが予定通り教育資金を受け取れる仕組みも安心感につながります。
必要な時期にまとまった資金を受け取れるため、計画的に使いやすいのもメリットです。
教育費を保険で準備するデメリット
保険を途中で解約すると、解約時期によっては解約返戻金が払い込んだ保険料を下回り、元本割れしてしまいます。急にお金が必要になって解約することのないよう、計画的に利用することが大切です。現在は低金利環境のため、保険の利回りは大きく期待できません。資産を効率的に増やしたい場合には、他の方法もあわせて検討してみましょう。
教育費を貯蓄する方法③「投資を活用」

金融商品に投資して、資産を増やしながら教育資金を準備する方法もあります。
投資を活用して教育費を準備する方法とは
教育費を投資で準備する場合、株式や投資信託を利用します。長期・積立・分散投資をすることで、リスクを抑えながら資産を育むことができます。
株式投資は難しいと感じる人には、投資信託がおすすめです。投資信託とは、投資家から集めたお金をひとまとめにし、プロが国内外の株式や債券などに分散して投資・運用してくれる商品です。少額からの積立投資も可能なため、初心者でも始めやすくなっています。
>>スマホでも始められる!投資信託は西日本シティ銀行がおすすめの理由をご紹介
教育費を投資で準備するメリット
投資を取り入れると、預貯金や保険よりも高い利回りを期待できます。長期積立による複利効果を活かせるのも大きな強みです。インフレに強い点も、将来の教育費高騰に備えるうえでメリットとなります。最近は少額から始められる投資商品も多く、柔軟に資産形成に取り組めるようになっています。
>>NISAで教育費を増やすなら、ぜひ読んでおきたい記事を厳選
【保存版】NISAについてわかりやすく解説|役立つ記事をまとめました
教育費を投資で準備するデメリット
投資には元本割れのリスクがあり、市場の動向によっては十分な資金を確保できない可能性があります。株式などは短期的には価格変動が大きく、知識や経験がないと利益を出すのが難しくなります。長期的な運用で、リスクを抑えながら資産を増やすことを考えましょう。
NISAつみたて投資枠の活用
教育費の準備に投資を取り入れる場合には、NISAの「つみたて投資枠」を活用しましょう。NISAとは、一定額までの投資で得られた利益が非課税になる制度です。NISAでの運用で得られた利益には、通常であればかかる20.315%の税金がかかりません。NISAを活用すれば、効率的に資産を増やせます。
2024年から始まった新NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円まで拡大しました。新NISAでは非課税保有期間も無期限化されています。制度を活用すれば、子どもが大学に進学するまでの間、安心して積み立てを続けられます。
教育費を貯蓄する方法④「家計の見直し」

教育費を準備するために、支出を減らす工夫も必要です。貯蓄すると決めたら家計の見直しもしましょう。
家計の見直しをするメリット
家計を見直せば、支出を減らせます。毎月の固定費(通信費・保険料・サブスクなど)を見直すだけで、数千円〜数万円単位の余裕が生まれることもあります。その分を教育費に回せば、無理のない積み立てができます。
>>固定費とは?おすすめの節約方法と見直すポイントもあわせて紹介
家計の見直しをするデメリット
節約のしすぎで生活の質を落としてしまうと長続きしません。食費や娯楽費を削りすぎると家族の満足度が下がり、教育費どころか生活全体に不満が募ることもあります。子どものためとはいえ、無理のない範囲で見直すことが大切です。
親ができる教育費サポートのポイントと成功例

教育費を準備する方法はいくつかありますが、いずれも継続することが大切です。ここからは、親が取り組める教育費準備のコツと成功例を解説します。無理なく続けられる工夫を取り入れ、子どもの将来にしっかり備えていきましょう。
子どもが生まれたらすぐに貯蓄を開始
教育費の貯蓄は早く開始するのがコツです。かかる金額の目安から貯蓄の目標額を設定しましょう。例えば、18年間で300万円を貯める場合、毎月の積立額は約1万4千円です。ところが、中学入学からの6年間で同じ300万円を貯めようとすると、毎月4万円以上が必要になります。子どもが生まれたときなど、早いタイミングで貯蓄を始めることで月々の貯蓄額を抑えられます。
教育費が不足する場合に利用できる選択肢
貯蓄が足りない場合でも、教育ローンや奨学金などの制度があります。特に日本学生支援機構の奨学金は利用者が多く、貸与型のほかに給付型もあります。どうしても不足する場合は、無理に家計を圧迫せず、制度の利用も検討すると安心です。
家計の見直しと貯蓄の自動化で着実に教育費を準備
家計を見直したうえで、貯蓄を自動化するのも有効です。自動積立定期やNISAのつみたて投資枠を利用し、給料から先取りで貯蓄ができる仕組みを作りましょう。
児童手当をすべて貯蓄して、教育費の準備に成功している方もいます。2024年10月以降、児童手当の支給期間は18歳(高校卒業)までに延長されました。高校卒業までに受け取れる児童手当の合計は230万円を超えるため、大学費用の大きな足しになります。
まとめ
子どもの教育費はトータルでは大きな出費となります。特に、大学進学費用はまとまった高額が必要になるので、事前の準備が不可欠です。かかる金額の目安を知って、預貯金、保険、投資などを活用して計画的に準備しましょう。家計を見直して貯蓄の自動化をすれば、無理なく資金の準備ができます。
*保険商品に関するご留意事項について
商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
投資信託のご留意事項(必ずご確認ください)
商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
◾️あわせて読みたい記事
・教育資金の貯め方にはコツがいる!必要な金額の目安や貯金におすすめな制度を紹介
・大学の学費は平均いくら?入学料や授業料総額と資金準備の方法を確認!
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、夫婦カウンセラー
大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。