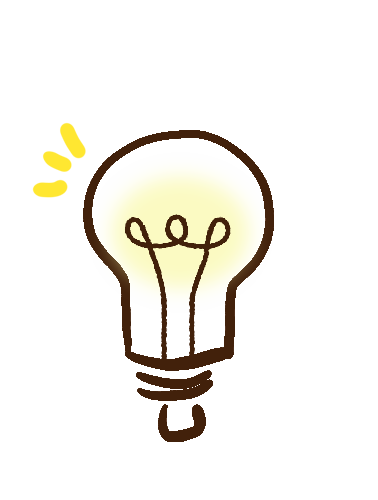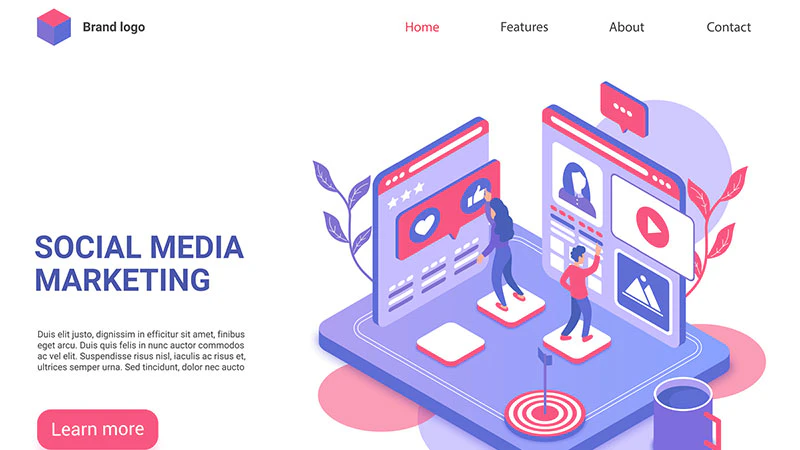社会人2年目の貯蓄は平均いくら?毎月の目安と貯めるコツをあわせて解説
社会人2年目になると、収入管理や貯蓄の計画が立てやすくなります。この段階で、多くの若手社員が真剣に貯蓄を開始しようと考えることでしょう。この記事では、社会人2年目の平均貯蓄額と、効果的な貯蓄継続のコツを紹介します。対象となるのは、高校や大学を卒業してすぐに就職した19歳から24歳までの方々です。
社会人2年目の貯蓄はいくら?

社会人2年目の平均貯蓄額については、正確なデータがないため一概には言い切れませんが、厚生労働省が29歳以下の若年層を対象に行った調査によると、平均貯蓄額は245.1万円であることが示されています。
以下では、社会人2年目の収入と貯蓄の割合を解説します。自身の収入や生活環境と比較して、目標となる貯蓄額の目安を検討しましょう。
参考サイト:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」
社会人2年目の平均収入はいくら?
社会人2年目が含まれる20~24歳の平均年収は273万円です。月収に換算すると22.75万円で、手取りでは税金などが引かれて17万円前後になります。
年収にはボーナスも含まれているので、毎月の給与はこれよりも低い方も多いです。一人暮らし、地方住まいなど、環境によって年収や貯蓄できる金額は違うので、自分に合った貯蓄方法を考えましょう。
参考サイト:国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査」
収入に対する貯蓄の割合の目安は?
社会人2年目の収入に対する貯蓄の目安は、収入に対して10~30%程度が理想的です。これ以上の金額を貯蓄すると食費や光熱費などを無理に節約しなければならず、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、一人暮らしか、二人以上の世帯で暮らしているかによって目安となる金額は変動することも理解しておきましょう。目安通りの貯蓄額を達成しているか、現在の支出を見直す必要があるのかなどを検討してみてください。
単身世帯の場合
社会人2年目の単身世帯の貯蓄の割合は、およそ10~20%です。一人暮らしは家賃や光熱費、食費などを自分でまかなう必要があるため、貯蓄できる金額の割合は低くなります。
例えば月の手取りが17万円の場合、10%であれば2万円程度、20%であれば3万円程度が目安です。都心に住んでいて家賃や生活費が高い場合は、20%の貯蓄が難しい可能性もあります。無理のない範囲で貯蓄額を検討しましょう。
二人以上世帯の場合
社会人2年目の二人以上世帯の収入に対する貯蓄の目安は、20~30%です。例えば手取りが17万円の場合、20%貯蓄するなら3万円程度、30%貯蓄するなら5万円程度の貯蓄を目安にしましょう。
実家暮らしは、家にお金を入れているかによって貯蓄できる金額が変動します。お金を入れない場合は、30%より高い割合を貯蓄に回せるでしょう。
パートナーや友人などと同居している場合は、生活費もふまえて貯蓄額を検討する必要があります。
社会人2年目が貯蓄を成功させるために意識すべきポイント

まだ収入が少ない社会人2年目の人が貯蓄を成功させるためには、やみくもに節約すればいいわけではありません。体を壊してしまったり、ストレスが溜まって反動で衝動買いをしたりしないよう、計画的に貯蓄を続けることが大切です。
ここからは、社会人2年目で貯蓄を続けるために意識すべきポイントを3つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目標の貯蓄額を決める
まずは目標の貯蓄額を決めましょう。何のために貯蓄をするのかを明確にすることで、毎月いくらの貯蓄が必要かを考えやすくなります。
前述にもある通り、社会人2年目が含まれる29歳までの平均の貯蓄額は245.1万円です。現在の貯蓄額によっては、平均額を目標にしてもいいでしょう。
ただし貯蓄額が高い人が平均値を押し上げている可能性もあるため、自身の収入や将来のお金の使い方と合わせて現実的な数字を目標にすることがおすすめです。
家計簿をつけて生活費の支出を把握する
貯蓄が思うようにできない方は、家計簿をつけて生活費の支出を把握しましょう。無駄使いを見直すことで、スムーズに貯蓄ができるようになります。
毎月必ず必要な家賃、通信費、光熱費などの固定費と、毎月変わる交際費や娯楽費などをわけることがおすすめです。支出を分類していくことで、自分のお金の使い方を見直せるようになるでしょう。
貯蓄専用の口座を持つ
貯蓄用の口座を持つことで、貯蓄がスムーズに進みます。給与が振り込まれる口座と使う口座、貯蓄をする口座をすべて一つにしていると、管理は楽ですがいくら貯まったのかを判断しにくいです。
また、口座に残っているお金を収入以上に使いすぎてしまうことは誰にでも起こり得ます。この問題を解決する一つの方法として、貯蓄専用の口座を設けることが有効です。毎月一定額をこの口座に自動で入金し、日常生活ではこの口座からは一切お金を引き出さないようにすることで、無意識のうちに貯蓄を増やすことができます。この方法により、計画的かつ強制的に資金を蓄えることが可能になります。
社会人2年目から上手に貯蓄を続けるコツ

社会人2年目はまだ収入が少ない場合が多いものの、飲み会や趣味などでお金を使ってしまいがちです。お金に余裕が生まれにくい社会人2年目でも、賢く貯蓄を続けるコツを紹介します。
先取り貯蓄をする
ある程度収支が把握でき、一定金額を貯蓄できそうな場合は、先取り貯蓄をしましょう。給与が入った時点で一定金額を貯蓄用の口座に移せば、残りの金額だけでやりくりすることになります。
自然とお金の使い方を見直すこともでき、収入が少なくても上手に節約生活ができるようになるでしょう。貯蓄用の口座を作らなくても、目標を書いた封筒や貯蓄箱などに入れて貯蓄のモチベーションを維持する方法もおすすめです。
定期預金口座を持つ
封筒や貯蓄箱などできちんと管理できる自信がないという方は、定期預金の口座を持つことがおすすめです。
定期預金の口座は、一定期間引き出せない、一定期間解約しないことで普通預金の口座よりも高い利息がつくので、しっかり貯蓄したい方には最適でしょう。
ただし、定期預金口座は途中で解約すると利息を得られなかったり、手続きが面倒だったりします。今後大きな買い物をする可能性がある方は、慎重に貯蓄額を考えましょう。
固定費を抑える
貯蓄のために支出を抑えるなら、固定費の見直しがおすすめです。家賃、光熱費、通信費など、毎月変動が少なく支出の割合が大きいものから見直していきましょう。
交際費や娯楽費など趣味やストレス発散の支出は毎月変動が激しく、無理に我慢をするとストレスにもなってしまいます。
固定費は最初に見直せばあとは考える必要がないので、支出の管理も楽になりますよ。
支出を把握する
社会人2年目から貯蓄をするなら、支出の把握は重要です。何にいくら使っているかわからないと、貯蓄額も決められません。月の最後に余った金額を貯蓄しようと思っても思うように貯められないこともあるでしょう。
無駄遣いを把握することで、日々のお金の使い方を見直して貯蓄しやすくなります。目標の貯蓄額に届かない場合は、スマホ会社を乗り換える、プライベートブランドの食品を選ぶなどの節約を意識してみましょう。
目標金額を決める
貯蓄を続けるには、目標金額を決めることが大切です。やみくもにお金を貯めていると、何のために我慢しているのかわからずにストレスになってしまいます。
反動で高い買い物をしたり、こまごまとした無駄なものを買ったりしてしまうこともあるでしょう。
「海外旅行をする」「結婚式を挙げる」など、将来に向けて明確な目標を持ち、お金を使うたびに思い出すことで、モチベーションを維持しやすくなりますよ。
ポイントを活用する
節約方法の一つとして、ポイントを活用することがおすすめです。ポイントを使えばお金が浮いて、その分を貯蓄に回せるようになります。
ポイントアップキャンペーンの際に日用品のストックを購入する、有効期限つきのポイントは無駄にしないなど、賢くポイントを使いこなすことが大切です。クレジットカードのポイントはもちろん、各店舗のポイントカードなども活用しましょう。
積立保険に加入する
積立保険に加入することも、貯蓄を続けるための選択肢として検討してみてください。積立保険は、毎月一定の保険料を納めることで解約時に高額な返戻金を受け取れます。
普通預金や定期預金の利息よりも高いバックがあるので、しばらくお金を使う予定がない方におすすめです。また、保険なら万が一病気になったときやけがをしたとき、働けなくなったときなどに、契約内容に応じて保険金を受け取れます。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税を活用することで、お得に貯蓄がしやすくなります。ふるさと納税は、実質負担額2,000円で地域のさまざまな返礼品を受け取れる制度です。寄付した金額は翌年の住民税と所得税で調整されるため、無駄がありません。
ふるさと納税の返礼品にはお米やティッシュなど、毎日の生活に役立つものが多数あります。お得な制度をとことん活用し、無理なく貯蓄を続けましょう。
昇給を目指す
社会人2年目で仕事に慣れてきたら、会社で昇給して収入を増やし、その分を貯蓄に回すことも考えましょう。
昇給するためには社内でしっかり成果を出し、周囲に認めてもらう必要があります。社会人2年目はまだまだ伸び代がある人が多い傾向にあるため、昇格するまでに時間もかかりますが、じっくりコツコツ貯蓄を続けたい方にはおすすめの方法です。就業規則を確認し、より早く昇給できるよう日々の仕事をこなしましょう。
まとめ
社会人2年目の平均の貯蓄額や貯蓄の割合を解説しました。社会人2年目はまだ収入が低く、自分で稼いだお金を自由に使えるという解放感から散財してしまいがちです。
将来を見据えて貯蓄を徹底したい方は、まずは目標を決め、収支を把握し、収入に見合った貯蓄額を決めることが大切です。自分に合う貯蓄方法、貯蓄を続けるコツを見つけることで、無理なく楽しみながら目標金額を目指せるでしょう。
*投資信託のご留意事項について
商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
■あわせて読みたい記事
・給与明細の3つの項目の見方は?仕組みや計算方法などもあわせて解説
・【年齢・男女別】年収と手取りの平均はいくら?増やす方法もあわせて紹介

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。