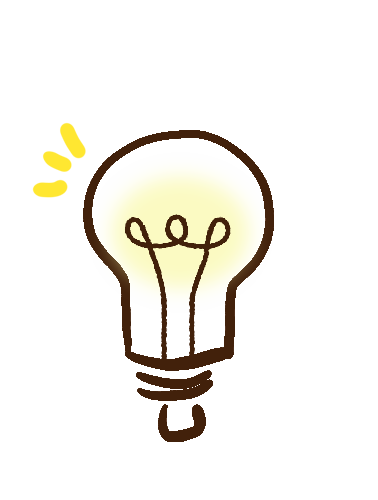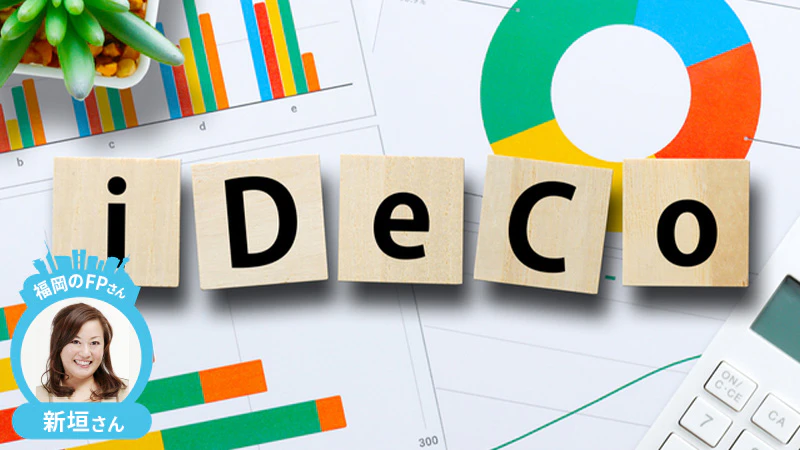確定拠出年金にかかる税金は?計算方法や受け取り方をわかりやすく紹介
確定拠出年金は、税金面でのメリットがある一方で、受け取り方によって課税される税金が異なるため、受け取り方法を慎重に選ぶ必要があります。 本記事では、確定拠出年金を受け取る際にかかる税金やその計算方法をわかりやすく紹介します。
>>iDeCo(個人型確定拠出年金)は、公的年金にプラスして個人で加入できる私的年金制度です。
目次
確定拠出年金は受け取り方で税金が変わる

確定拠出年金を受け取る方法には、「年金形式」と「一時金」の二つの選択肢があります。受け取り方によって税金の扱いが異なるため、どちらにするか慎重に選ぶことが大切です。
毎月年金で受け取る場合は雑所得として総合課税されますが、一時金で受け取る場合は退職所得として分離課税され、税率が軽減されます。それぞれの受け取り方は併用することもでき、上手に組み込めば税負担を軽減できる場合もあります。
二つの受け取り方の違いを理解し、税金の負担を軽減できる方法を探してみましょう。
年金で受け取る場合は雑所得として総合課税
確定拠出年金を毎月年金形式で受け取ると、受け取った金額は雑所得として扱われ、総合課税が適用されます。
公的年金の雑所得の計算式は「公的年金等の雑所得=収入金額-公的年金等控除額」です。収入金額から公的年金等控除額を差し引いた後に課税されるため、控除額が大きいほど税負担を軽減できます。そのため、年齢やその他の所得によって最終的な税額が決まります。
年金額が増えると累進課税の影響を受けるため、毎月の受け取り金額を調整することで税負担を最小限に抑えられます。
一時金で受け取る場合は退職所得として分離課税
確定拠出年金を一時金として受け取る場合、税制上は退職所得として扱われ、分離課税が適用されます。退職所得は収入金額から退職所得控除額を引き、その金額を1/2にして税額を算出します。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
なお、退職所得企業の勤続年数によって退職所得控除の額は変わります。
- 勤続年数が20年以下:40万円(80万円に満たない場合には80万円)×勤続年数
- 勤続年数が20年以上:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
一時金と年金の併給も可能
確定拠出年金は、一時金と年金の併給も可能で、税負担の軽減に役立ちます。一時金の金額が退職所得控除を上回る場合でも、年金と併用することで、税負担を抑えながら受け取ることが可能です。
退職所得控除をフル活用できるため、年金部分を雑所得として受け取る場合でも、税金を効率よく管理できるでしょう。
確定拠出年金を年金形式で受け取る際の注意点

ここからは、確定拠出年金を年金形式で受け取る際の注意点を詳しく見ていきましょう。
年齢による公的年金等控除の控除額の違いに注意する
確定拠出年金を年金形式で受け取る場合、年齢によって公的年金等控除額が異なるため、年齢に応じた受け取り方法を選ぶことが大切です。
公的年金等控除は、年金を受け取る際に課税される金額から差し引かれ、年齢を重ねるごとに控除額が増加します。例えば、65歳未満と65歳以上では控除額が異なるため、受け取りのタイミングを慎重に選択することが大切です。
年齢に応じた控除額を最大限活用して受け取る金額を調整することで、税金の負担を抑えられるでしょう。
雑所得は所得税・住民税の課税対象になる
確定拠出年金を年金形式で受け取る場合、受け取った金額は雑所得として扱われ、所得税と住民税の課税対象となります。
雑所得は他の所得と合算され、累進課税方式に従って税率が決まります。税率が高くなると税負担が大きくなるため、年金を受け取る金額が他の所得と合算される点に注意しましょう。
また、住民税も課税対象となり、税負担が増える可能性があります。年金額や受け取り時期を考慮して、税負担を抑えることも大切です。
受取期間の違いによる税負担の違いに注意する
確定拠出年金を年金形式で受け取る際、受取期間の長さによって税負担が変わります。
受取期間を長期に設定すると、1年あたりの受取額が少なくなり、累進課税の影響を抑えられるため、毎年の税負担が比較的小さくなる可能性があります。一方、短期間で受け取ると1年あたりの受取額が増え、累進課税により適用される税率が高くなる可能性があるため、結果的に税負担が大きくなることがあります。
計画的に受取期間を決めることで、税負担を抑えつつ、効率的に年金を活用することができます。
確定拠出年金を一時金で受け取る際の注意点

確定拠出年金を一時金形式で受け取る際は、退職所得控除を最大限に活用することが大切です。
退職所得控除の適用条件と計算方法に注意する
確定拠出年金を一時金として受け取る場合、退職所得控除を適用できます。しかし、退職所得控除を適用するためには、いくつかの条件と計算方法に注意が必要です。
まず、退職所得控除を適用するためには、退職金や一時金を受け取る者が退職していることが前提条件です。
税制改正や各年ごとの条件変更があるため、最新の情報を把握して適切に対応することも忘れないようにしましょう。
他の退職所得と合算される場合は課税額が高くなる
確定拠出年金を一時金で受け取る場合、他の退職所得と合算されることがあります。
例えば、同じ年度に他の退職金や一時金を受け取った場合、それらが退職所得として合算されて最終的な課税額が高くなる可能性があります。このため、確定拠出年金を受け取るタイミングや金額の調整を行うことが大切です。
退職所得は分離課税されるため、他の所得とは分けて税金を計算します。しかし、複数の退職所得が合算されることで、税金が想定以上に高くなる可能性があることは理解しておきましょう。
翌年の住民税への影響を見落とさない
確定拠出年金を受け取った際の税負担は、所得税だけでなく翌年の住民税にも影響を与えます。
所得税はその年の収入に基づいて課税されますが、住民税は前年度の収入に基づいて計算されます。そのため、確定拠出年金を一時金として受け取ると、翌年の住民税が増額される可能性があるのです。
この影響を避けるためには、確定拠出年金を受け取るタイミングや金額を考慮し、住民税の負担が一時的に増えないように工夫する必要があります。住民税の支払いは毎年決まったタイミングでおこなわれるため、その影響を事前に把握しておくと予算を立てやすくなります。
確定拠出年金を運用する際の税金以外の注意点

確定拠出年金の運用を行う際には、税金以外にも注意すべき点があります。運用コストやリスク、引き出し制限などを理解し、適切に管理することが重要です。
口座管理手数料がかかる
確定拠出年金を運用する際には、口座管理手数料が発生することに注意が必要です。
確定拠出年金は、金融機関(運営管理機関)を通じて運用されるため、その管理費用として手数料がかかります。この手数料は、運用する金額や金融機関によって異なりますが、長期的に見ると大きな負担になるかもしれません。
特に、受け取り開始時期を遅らせる場合は運用期間が長くなり、その間も手数料がかかるため、どのタイミングで年金を受け取るのかを慎重に判断する必要があります。
元本割れする可能性もある
確定拠出年金を運用する際には、元本割れのリスクを十分に理解しておくことが大切です。
確定拠出年金では、株式や債券、投資信託などさまざまな金融商品を組み合わせて運用できます。しかし、市場の変動が大きい時期や、選択する金融商品の運用成績が悪い場合、元本を下回る可能性があることに注意が必要です。
市場の変動が大きい時期や運用方法が不適切な場合、元本割れが発生する可能性が高くなります。元本割れを防ぐためには、リスク分散を行い、安定した成長が期待できる運用方法を選ぶことが必須です。長期間運用を続ければ元本割れの影響を抑えることができる場合もあるため、長期的な視野での運用計画を立てていきましょう。
原則60歳まで引き出せない
確定拠出年金は、原則として60歳まで引き出すことができません。
確定拠出年金は、老後の資産形成を目的として積み立てるための制度です。そのため、確定拠出年金の積立とは別に、日常の生活費や緊急時に備えた資金を別途確保しておくことが重要になります。
確定拠出年金は拠出時も税金のメリットがある

確定拠出年金は、拠出時にも税金のメリットがあります。掛金の所得控除や運用益の非課税措置を活用することで、税負担を軽減しながら効率的に資産を積み立てることができます。
掛金が全額所得控除の対象
確定拠出年金の掛金は、全額が所得控除の対象です。掛金を拠出することで、現役時代の税負担の優遇を受けられます。
税金を効果的に抑えつつ、将来に向けて資産を積み立てられるため、税制上非常に有利な制度といえるでしょう。特に、年収が高い場合はそのメリットが大きく、所得税の軽減効果を実感しやすいです。
運用益に税金がかからない
確定拠出年金における大きな税制メリットの一つは、運用益に税金がかからないことです。通常、金融商品における利益には税金が課されますが、確定拠出年金では運用中の利益(配当金や売却益など)には課税されません。この非課税措置により、運用益をそのまま再投資でき、長期間にわたって資産を効率的に増やすことが可能 です。
ただし、確定拠出年金の資産は受取時に課税されるため、受け取り方(年金形式もしくは一時金形式)によって税負担が異なる ことに注意が必要です。
まとめ
確定拠出年金には、税制上の大きなメリットがある一方で、受け取り方や運用方法によって税金の負担が変わるため、仕組みを十分理解しておくことが大切です。年金形式や一時金形式で受け取る際の税負担の違い、退職所得控除や公的年金等控除の活用方法など、選択肢をしっかりと見極めましょう。
確定拠出年金は将来の資産形成に役立ちますが、税制をうまく活用し、それぞれのライフプランに合わせて使うことが、よりよい資産形成を実現するためのポイントです。
西日本シティ銀行窓口でのご相談はこちらからご予約ができます↓
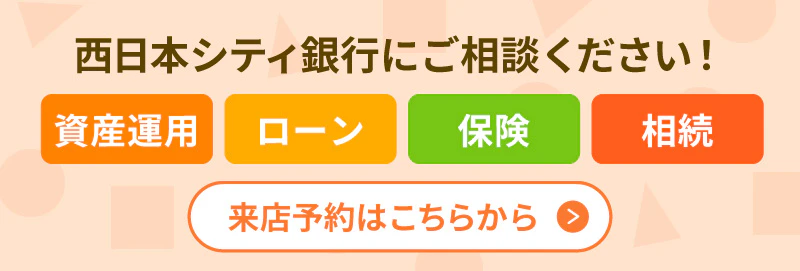
■あわせて読みたい記事
・NISAとiDeCoの賢い活用法|上手に使い分けるためにもライフプランを作成しましょう!
・専業主婦(夫)がiDeCoを始めるメリットとは?制度の仕組み・注意点etc.を徹底解説
投資信託のご留意事項(必ずご確認ください)
商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。