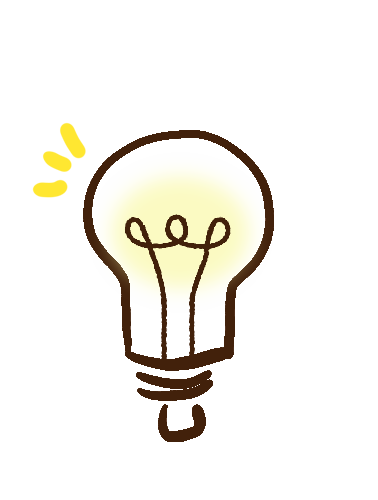不妊治療の費用はいくら?福岡県で利用できる保険制度も知って自己負担額を減らそう
不妊治療には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。不妊治療は保険適用外になるものもあり、高額になりやすい傾向があります。しかし、近年では保険適用の範囲が広がっており、制度を利用することで助成金を受け取れるケースもあります。この記事では不妊治療の費用を解説します。不妊治療を検討する上で参考にしてみてください。
不妊治療の平均費用と治療内容

不妊治療の費用は、選択する治療法や保険適用の有無によって大きく異なります。2022年4月から保険適用の不妊治療の範囲が拡大され、不妊に悩む家庭の経済的な負担が軽減されました。
タイミング法や人工授精などの初期段階の比較的安価な治療から、体外受精や顕微授精といった高度な生殖補助医療まで、さまざまな治療法の選択肢が広がっています。それぞれの治療法とその費用(保険が適用された場合)の一例を詳しく見ていきましょう。
不妊治療の方法と費用の一例
- タイミング法…約750円
- 人工授精の費用…約5,460円
- 採卵術の費用…約9,600円
- 体外受精の費用…約9,600円
- 胚凍結保存の費用…約15,000円~
- 顕微授精の費用…約11,400円~
- 精巣内精子採取術の費用…約37,200円~
タイミング法は約750円
タイミング法は、不妊治療の第一段階として一般的な方法です。医師の指導のもとで排卵日を特定し、そのタイミングに合わせて性交をおこなうことで、妊娠の可能性を高めます。
排卵日は、基礎体温測定やホルモン検査、超音波検査などを用いて予測され、必要に応じて排卵誘発剤が処方されることもあります。
タイミング法では、3カ月に1回「一般不妊治療管理料」として約750円がかかります。これに加えて、超音波検査や薬剤費などが発生することもあります。
人工授精の費用は約5,460円
人工授精は、タイミング法で妊娠に至らなかった場合に行われる治療法です。排卵のタイミングに合わせて、精子を子宮内に直接注入し、受精の可能性を高めます。
自然妊娠よりも精子が子宮内に到達しやすくなるため、特に精子の運動率が低い場合や、性交障害がある場合に有効です。
身体への負担は少ないものの、人工授精の成功率は1回あたり約5~10%とされており、回数を重ねると費用がかさむ点には注意が必要です。
保険適用時の費用は約5,460円ですが、処置内容によって加算が発生することがあります。
採卵術の費用は約9,600円
採卵術は、体外受精や顕微授精をおこなう際に必要な処置で、卵巣から卵子を取り出す手術です。通常、排卵誘発剤で複数の卵胞を成長させた後、経膣超音波ガイド下で針を用いて卵胞液とともに卵子を吸引します。
採卵は比較的負担の大きい処置であり、一時的な下腹部痛や出血が起こることがあります。また、まれに卵巣過剰刺激症候群などの副作用が発生する可能性があるため、慎重な検討が必要です。
基本費用は約9,600円ですが、局所麻酔・全身麻酔の選択、採取する卵子の数、培養方法によって加算されるため、総額はさらに高くなることがあります。
体外受精の費用は約9,600円
体外受精は、卵巣から採取した卵子と精子を体外で受精させ、受精卵を子宮に戻す治療法です。タイミング法や人工授精では妊娠が難しい場合に選択されます。
1回あたりの成功率は20~30%程度で、複数回の治療が必要な場合があります。
保険適用時の基本費用は約9,600円ですが、排卵誘発剤や培養費、胚移植などの費用が加算されるため、最終的な費用は高額になることが一般的です。
胚凍結保存の費用は約15,000円~
胚凍結保存は、体外受精や顕微授精によって得られた受精卵を凍結し、将来の胚移植のために保存する方法です。複数回の採卵をおこなわずに済むため、女性の身体的・経済的負担を軽減できます。適切なタイミングで移植をおこなうことで、妊娠率の向上が期待できるというメリットもあります。
胚凍結保存管理料として導入時に約15,000円~かかり、この費用は凍結する胚の数によって変動します。保存を継続するための年間維持管理料は約10,500円で、更新のたびに維持費が発生します。
顕微授精の費用は約11,400円~
顕微授精は、精子の運動率が極端に低い場合や、受精障害がある場合に行われる高度な治療法です。通常の体外受精では受精が難しい場合でも、顕微鏡を用いて1つの精子を直接卵子に注入することで、受精の確率を高めます。
成功率は体外受精と同程度ですが、卵子への負担がやや大きいため、医師と相談しながら慎重に治療を進めることが推奨されています。
保険適用時の基本費用は約11,400円~ですが、使用する技術や培養環境によって加算が発生します。
精巣内精子採取術の費用は約37,200円~
精巣内精子採取術は、無精子症の男性に対して精巣から直接精子を採取する手術です。
手術には主に2種類の方法があり、通常のTESEでは精巣の一部を採取し、顕微鏡で精子を探します。一方、顕微鏡を用いた精巣内精子採取術は、精子が存在しやすい部分を特定しながら採取するため、精子の回収率が向上するメリットがあります。
しかし、その分手術時間が長くなり、費用も高額になる傾向があります。費用は単純な精巣内精子採取術が約37,200円、顕微鏡を用いた手術が約73,800円です。
不妊治療の保険適用範囲は広がっている

かつて不妊治療は保険適用外の方法が多く、高額な費用が必要でした。子どもができない家庭にとって長期間の高額な治療は経済的な負担が大きく、妊娠をあきらめてしまうケースもあります。
近年は不妊治療の保険適用範囲が広がっています。以下では、保険適用内の不妊治療の方法や条件を解説します。
現在保険適用内の不妊治療法
現在、保険適用内で受けられる不妊治療法は多岐にわたります。
一般不妊治療として代表的なタイミング法はもちろん、人工授精や生殖補助医療も対象です。生殖補助医療の手法としては、採卵や採精、体外受精、顕微授精などが挙げられます。
受精卵や胚の培養、胚の凍結保存といった技術も保険適用の対象です。これらの中には、これまで高額な費用がかかっていたものも多く、費用負担の軽減は今後の不妊治療の大きな助けになるでしょう。
不妊治療の保険適用の条件
不妊治療が保険適用となるには、いくつかの条件が定められています。まず、保険適用を受けるためには女性が43歳未満である必要があります。さらに、40歳未満の場合は、子ども一人につき通算6回までの治療が適用されます。これに対して、40歳から43歳の間では、子ども一人につき通算3回までの治療が保険適用の対象です。
ただし、保険適用される治療内容や条件は細かく設定されているため、医療機関や自治体の情報を確認しましょう。
保険適用前に受けていた治療も続けて受けられる?
保険適用範囲が拡大されたことで、それ以前に保険適用外として治療を受けていた場合でも、条件を満たせば保険適用として治療を続けることが可能です。例えば、以前から体外受精や顕微授精を行っていた場合でも、条件を満たせば保険適用の恩恵を受けられます。
ただし、保険適用を受け続けるためには、年齢制限や治療回数の上限といった条件をクリアしている必要があります。これらの条件から外れる場合や保険適用外の治療を組み合わせる場合は注意を要します。
保険適用拡大に伴う制度の変化
不妊治療への保険適用が拡大されたことに伴い、これまで高額な治療費の負担軽減策であった「特定不妊治療助成制度」が2022年3月をもって原則終了となりました。この変更により、以前助成金を利用していた方も、現在では主に保険診療で治療を進めるようになっています。
福岡県で不妊に悩む方への先進医療支援事業

一方「先進治療」に分類されるような一部の治療については、保険適用外となるケースも。こうしたケースにおいては費用負担を軽減するために、国や自治体が支援事業(助成金制度)を設けている場合があります。
福岡県では、不妊治療にかかる費用を負担する支援として先進医療支援事業があります。先進医療支援事業は、保険診療による1回の特定不妊治療と併用して実施した先進医療にかかる費用の一部を助成する制度です。ただし、保険診療分や人工授精などの一般不妊治療は対象外となります。助成を受けられるのは、先進医療にかかった費用の7割、5万円までで、助成を受けるには申請が必要です。
助成される人の条件
先進医療支援事業の対象となるのは、特定不妊治療開始日に夫婦であることが条件です。これには事実婚も含まれ、その場合は出生した子を認知する意向があることも条件です。
また、特定不妊治療開始日の妻の年齢が43歳未満である必要があります。特定不妊治療開始日から申請日までの期間、継続して夫婦の双方、またはいずれかが福岡県内の市町村に住所を有していることも条件です。
対象の先進医療
福岡県の先進医療支援事業の対象となるのは、以下の先進医療です。
________________________________________
福岡県の先進医療支援事業の対象の不妊治療
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス)
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査1(子宮内膜受容能検査、ERA)
- 子宮内細菌叢検査1(子宮内細菌叢検査、EMMA、ALICE)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 二段階胚移植術(二段階胚移植法)
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
- 子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査、ERPeaK)
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術 タクロリムス投与療法(不妊症患者に対するタクロリムス投与療法)
- 着床前胚異数性検査
まとめ
不妊治療は保険適用外のものが多く、自己負担が高額になるケースも少なくありません。一般的な家庭にとって、長期間に及び高額な費用を支払い続けるのは現実的ではないでしょう。しかし、保険適用の範囲は拡大されつつあり、各自治体も不妊治療に関する助成金や補助をおこなっています。
福岡県でも不妊治療に関する助成制度は用意されているので、現在不妊でお悩みの方はぜひ活用してみてください。
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。