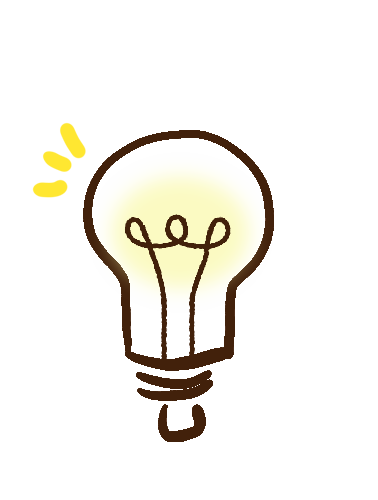インデックス投資とは?メリットやデメリット、選び方などをわかりやすく解説
将来のお金の不安を解消するために、資産形成を目的とした投資を考える人が増えています。一方で、リスクへの不安からなかなか踏み出せない人も少なくありません。そこで本記事では、初心者でも安定した運用が期待できるインデックス投資について説明し、その選び方も紹介します。ぜひ、資産運用を始める際の参考にしてください。
インデックス投資とは

インデックス投資とは、特定の指数(インデックス)の値動きに連動する運用成果を目指す投資手法のことです。ここではインデックスについてさらに詳しく解説し、インデックス投資とアクティブ投資の違いも説明します。
インデックスって何?
「インデックス」には「索引」「指数」「指標」などの意味があります。投資におけるインデックスとは、具体的にどのようなものなのでしょうか。以下に代表的なインデックスを紹介します。
代表的なインデックス
インデックスとは、株式市場などの全体的な値動きを示す指数のことです。代表的なインデックスには、日経平均株価(日経225)やTOPIX(東証株価指数)、アメリカのダウ平均(ダウ工業株30種平均)、ナスダック総合指数、S&P500指数などがあります。
日経平均株価(日経225) | 日本経済新聞社がプライム市場に上場する企業の中から225銘柄を選定し、その株価をもとに算出した指数です。TOPIXと並んで日本経済の動向を表す指標となっています。 |
|---|---|
TOPIX(東証株価指数) | 東証プライム市場の全銘柄を対象にした株価指数です。各銘柄の時価総額(株価×発行済株式数)を合計し、基準日の時価総額で割って算出されています。これにより株式市場全体の動きを把握することができます。 |
ダウ平均 | 米国株式市場を代表する30銘柄から構成される株価指数で、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が算出・公表しています。 |
ナスダック総合指数 | ナスダック(NASDAQ)市場に上場している代表的な約3,000銘柄(※銘柄数は変動します)を対象とし、時価総額加重平均で算出した指数です。特にハイテク関連の企業の割合が高いことで知られています。 |
S&P500指数 | 米国の代表的な企業500社の株価をもとに算出される株価指数です。米国株式市場全体の約8割の時価総額をカバーしており、市場全体の動向を把握するのに適しています。 |
株価指数以外にも、東証に上場している不動産投信(J-REIT)全銘柄を対象とする指数や国債や社債などを対象として算出される指数もあります。こうした銘柄の構成は、インデックス投資の方向性を決める重要なポイントです。
インデックスファンドとは?
インデックスファンドとは、インデックス投資の手法に基づいて運用される投資信託のことです。例えば、日経平均株価のインデックス投資を自分で行うには、原則として構成する225銘柄に適切な比率で投資しなければなりません。その点、インデックスファンドを使えば、日経平均株価に連動する1つのファンドを購入するだけで、同様の投資効果が期待できます。
インデックスファンドは、分散投資の効果により、個別株投資に比べてリスクを抑えられる傾向がありますが、元本保証ではなく、市場全体の下落時には損失が発生する可能性もあります。
アクティブ投資との違い
アクティブ投資とは、インデックスを上回る投資成果を目指す手法のことです。また、アクティブ投資を行っている投資信託のことを、アクティブファンドといいます。
アクティブファンドは、インデックスに連動した投資ではなく、運用担当者が有望と判断した銘柄に重点的に投資し、高いリターンを目指します。インデックスに含まれない銘柄も投資対象となる場合があります。アクティブファンドは運用担当者による調査や分析が行われるため、インデックスファンドよりも信託報酬が高くなる傾向にあります。
インデックス投資のメリット

日経平均株価やS&P500など、市場の動きを示す代表的なインデックスは情報も得やすく、これらに連動するインデックス投資は未経験者でも比較的始めやすいとされています。ここでは、インデックス投資の主なメリットについてまとめました。
低コストで運用が可能
インデックスファンドは、特定の指数に連動する運用成果を目指して設計されています。そのため、専門家が独自に銘柄を選定・分析するアクティブファンドに比べて、保有中にかかる手数料(信託報酬)が一般的に低く設定されています。
投資信託を購入する際に販売手数料がかかる場合がありますが、「ノーロード」と呼ばれる販売手数料が無料の投資信託もあります。ノーロードのインデックスファンドを選ぶことで、より低コストでの運用が可能になります。
投資の手間がかからない
インデックス投資では、連動対象とする指数に合わせて運用されるため、投資家自身が構成銘柄やその割合を頻繁に検討する必要がありません。また、日経平均株価やS&P500といった代表的なインデックスの情報をニュースなどで見るだけで、おおよその値動きを把握できます。
インデックス投資は、多くの場合、投資信託(インデックスファンド)を購入して行います。投資家自身が個別の銘柄を選ぶ必要がなく、運用は専門家に任せられます。そのため、投資のための情報収集や調査などの手間もかかりません。
分散投資でリスクが抑えられる
インデックス投資は、日経平均株価やS&P500などの指数に連動するように運用されます。構成銘柄に広く分散投資されるため、1つの銘柄が暴落しても影響を受けにくく、相対的にリスクが低減されます。
個別銘柄で分散投資をしようとすると多額の資金が必要になることがありますが、インデックスファンドなら1つの商品を購入するだけで手軽に分散投資が可能です。そのため、個別株に集中投資する株式投資に比べて、一般的に価格変動リスクが低減される傾向にあります。
少額から購入できる
株式投資で個別株を購入する場合、通常は100株単位での取引となるため、1銘柄でも数万円から数十万円の資金が必要になることがあります。
しかし、インデックスファンドであれば、商品によっては100円や1,000円といった少額から購入することが可能です。投資が初めてで、大きな金額を投じることに不安を感じる人でも、気軽に始めやすいでしょう。
少ない資金から始めて、徐々に投資に慣れていきながら、自身のペースで資産形成を目指せるのもインデックス投資の魅力の一つです。
インデックス投資の注意点

投資未経験でも始めやすいインデックス投資ですが、メリットだけでなく注意点もあります。あとで「こんなはずではなかった」とならないよう、デメリットをしっかり確認しましょう。
短期間でのリターンは望めない
インデックス投資は、複数の銘柄に分散投資することで、市場全体の平均的なリターンを目指す運用手法です。短期間で大きなリターンを得るのは難しく、基本的に長期視点で取り組む必要があります。
そのため、短期間で高リターンを狙いたい人には、インデックス投資は必ずしも適していません。
暴落時には影響を受ける
インデックス投資は分散投資の効果により、構成銘柄の一部が値下がりしても、全体への影響は限定的です。しかし、リーマンショックや新型コロナウイルス感染症のパンデミック時のような、市場全体が大きく下落する局面では、インデックス投資もその影響を避けられません。
売買のタイミング次第では元本割れすることもあります。長期で保有する場合、こうした市場全体の大きな下落を経験することも想定しておく必要があるでしょう。そうしたリスクも含めて、資産運用を考えることが大切です。
インデックスを超えるリターンは狙えない
インデックス投資は長期間で市場の成長に合わせた資産増を目指せますが、日経平均などのインデックスに合わせて運用するため、それを上回るリターンは期待できません。インデックスを上回るリターン獲得を積極的に目指すのは、アクティブ投資の領域です。
ただし、アクティブ投資も必ずリターンが保証されているわけではなく、インデックスを下回る結果になることもあります。インデックス投資は、市場平均以上の高リターンを積極的に目指さない代わりに、運用成績が市場平均から大きく乖離するリスクも抑えられていると一般的に考えられています。これらの特徴やメリット・注意点を理解しておくことが大切です。
インデックスファンドの選び方

インデックスファンドは、投資対象によってさまざまな種類があります。初めて購入する際は、どれを選べばよいのか迷うこともあるでしょう。そこで、インデックスファンドを選ぶ際のポイントをまとめました。
自分の運用志向と合うファンドを探す
インデックスファンドには、株式だけでなく債券や不動産などを投資対象とするものもあり、国内だけでなく海外の資産にも投資できます。それぞれ期待されるリターンや価格変動リスクの大きさが異なるため、自身に合ったファンドを選ぶことが重要です。
例えば、リスクをできるだけ避けたい人は、値動きが安定している債券を選ぶとよいでしょう。また、大きなリターンを狙いたい場合は、経済成長が見込まれる新興国に投資するファンドを検討するのも選択肢の一つです。
コストをチェック
インデックスファンドを購入する前にチェックしておきたいのが、コストです。例えばコストには「購入手数料」、売却時にかかる場合がある「信託財産留保額」、保有中にかかる「信託報酬」があります。これらは運用益に影響するため、事前にしっかり確認しましょう。
信託報酬は、ファンドを専門家に管理・運用してもらうための費用で、一般的に年率で表示されます。同じ指数に連動するインデックスファンドでも、信託報酬が異なることがあるので、複数のファンドを比較検討することが大切です。購入時の手数料や信託財産留保額が無料のファンドも多く存在します。
運用実績や純資産総額を確認
投資対象や運用コストなどを比較検討して候補となるファンドが見つかったら、その運用実績も確認しましょう。交付運用報告書や月次レポート、ファンドのウェブサイトなどで、過去のパフォーマンス(基準価額の推移や騰落率など)を確認し、対象インデックスとの連動性などを参考にします。ただし、過去の実績は将来の運用成果を保証するものではありません。
また、純資産総額も必ず確認しましょう。純資産総額はファンドの規模を表す指標で、あまりに少ない場合や減少し続けている場合は、安定した運用が難しくなったり、繰上償還(ファンドの運用が終了)されたりする可能性が高まります。初心者がインデックスファンドを選ぶ際は、純資産総額が十分に大きく、運用実績のあるファンドを選ぶことで、安定した運用が期待しやすくなります。
購入先を選ぶ
自分に合ったインデックスファンドを見つけたら、いよいよ購入です。しかし何から始めればよいかわからない人もいるでしょう。そこで、インデックスファンドの一般的な購入手順と、購入できる金融機関の一例について紹介します。
インデックスファンド購入手順
インデックスファンドを購入するためには、まず投資信託を購入できる口座を開設する必要があります。インデックスファンドは多くの証券会社や一部の銀行で取り扱っているため、自身が相談しやすく、使い勝手の良い金融機関を選ぶことがポイントです。口座を開設したら、購入資金を入金し、希望のファンドを購入します。
取り扱っている投資信託の数が多くて目当てのファンドが見つけにくい場合は、金融機関のウェブサイトなどで「インデックスファンド」と検索したり、「日経225」「S&P500」といった具体的な指数名で絞り込んだりするとよいでしょう。商品名だけでは内容が判断しきれない場合は、必ず「交付目論見書」を読んで、投資対象やリスク、手数料などを確認してください。
まとめ
インデックス投資は特定の指数に連動する投資方法です。短期間で大きなリターンは期待できないデメリットがありますが、長期的に安定して運用できるメリットもあります。仕組みを理解すれば、値動きもわかりやすく、低コストで始められます。これから投資を始めたい人は、ぜひ検討してみてください。

投資信託のご留意事項(必ずご確認ください)
商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
■あわせて読みたい記事
・【初心者必見】投資信託の始め方ガイド!対象の種類や運用方法、気をつけるポイント
・米国株式とは?「S&P500」、「NYダウ」、「NASDAQ総合」の比較
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学卒業後、システムエンジニアを経て通信機器商社の経営戦略室で新規事業の立ち上げに参画。退社後はシステム会社の代表取締役に就任し、パソコン通信サービスを展開。1996年に著書『わかる!イントラネット』執筆後はフリーランスとして活動。事業経験とFP資格を活かしビジネス系ライターとして複数メディアで執筆中。