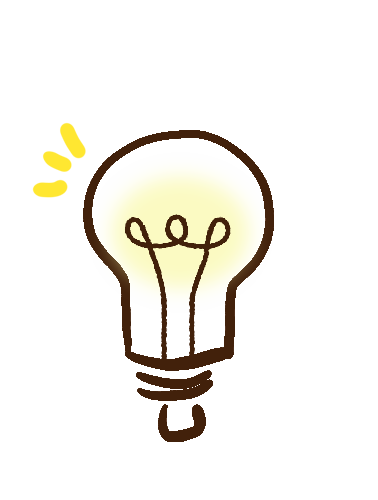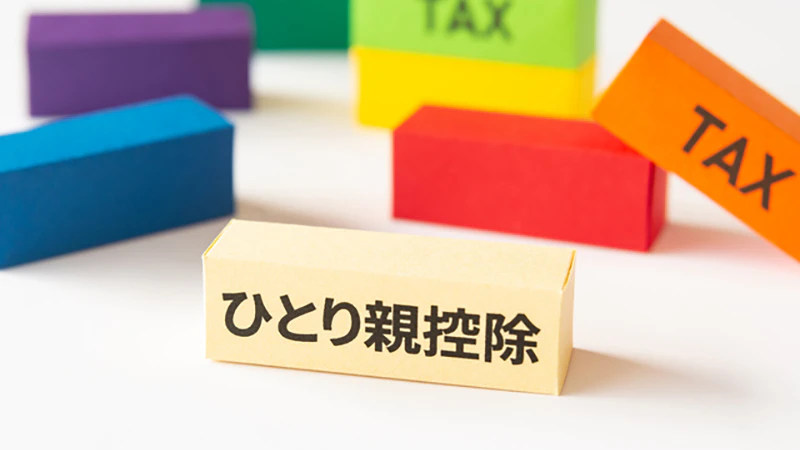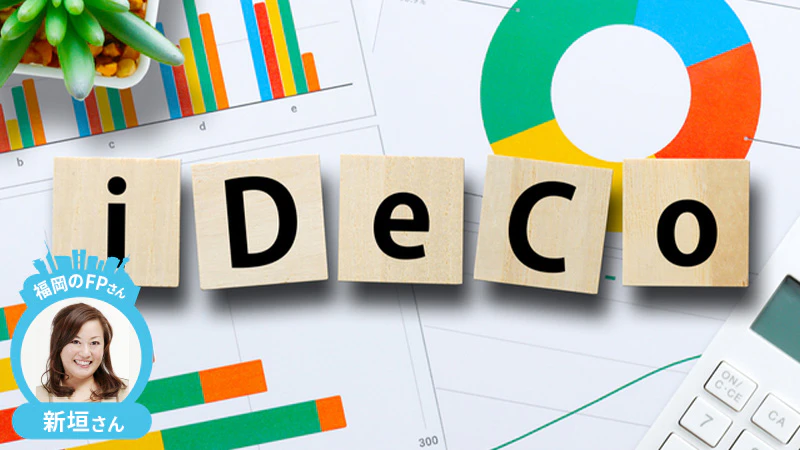子どものお小遣いの平均はいくら?福岡県の世帯別の金額と渡し方も解説
子どものお小遣いの年代別、世帯別の平均額と、お小遣いの渡し方やお小遣いを渡す際のポイントも紹介します。福岡県のお小遣いの平均も紹介するので、今後子どもにお小遣いを渡す必要がある場合は、ぜひ参考にしてみてください。
子どものお小遣いの平均額を年代別に解説

子どものお小遣いの平均額を、小学生、中学生、高校生と年代別に紹介します。各家庭の年収やお小遣いの制度によって金額は異なるので、以下で解説する金額はあくまでも目安としてお考えください。
出典:家計調査「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」
小学生低学年のお小遣いの月平均は2,213円
小学生低学年のお小遣いの一か月平均は、2,213円です。小学生の中でも高額な結果ですが、あくまでも目安となります。2,000円は渡しすぎだと感じる場合は、家族間で話し合って決めてみてください。
なお、保護者の収入別のお小遣いの平均の内訳は、以下のとおりです。

小学生中学年のお小遣いの月平均は1,751円
小学生中学年のお小遣いの一か月平均は、1,751円です。保護者の収入別の平均額は、以下のとおりです。

小学生高学年のお小遣いの月平均は2,054円
小学生高学年のお小遣いの一か月平均は、2,054円です。保護者の収入別の平均は、以下のとおりです。

中学生のお小遣いの月平均は3,860円
中学生のお小遣いの一か月平均は、3,860円です。保護者の収入別の平均は、以下のとおりです。

高校生のお小遣いの月平均は6,629円
高校生のお小遣いの一か月平均は、6,629円です。保護者の収入別の平均は、以下のとおりです。

福岡県のお小遣いはいくら?

福岡市の二人以上世帯の月の収入は平均501,712円で、12か月に換算すると6,020,544円です。
上記の表を参考にすると、子どもの年代別のお小遣いの平均は以下のとおりとなります。
参考:家計調査「家計収支編 二人以上の世帯」

子どものお小遣いの渡し方や頻度

子どものお小遣いの金額は、渡し方や頻度によっても異なります。渡し方は子どもとよく話し合い、お互いに納得できる形でお金を渡せるようにしていきましょう。
お小遣いの渡し方や頻度について、それぞれの特徴を解説します。
定額制
定額制は、一定期間に同じ金額のお小遣いを渡す方法です。毎月、毎週など、子どもと決めた頻度でお小遣いを渡していきます。子どもがまだお金の管理が難しい年齢であれば、月に一度まとまった金額を渡すより、週に一度など短いスパンで少額ずつ渡すこともおすすめです。
定額制は、お金の管理を学ぶのに最適な方法です。しかし、なにもしなくてもお金がもらえるので、お金のために努力をする習慣が身に付きにくくなるデメリットもあります。
都度制
都度制は、子どもがお金が必要なときにお小遣いを渡す方法です。勉強で必要なものがあるとき、友達と遊びに行くときなど、状況に応じて金額も変動します。
都度制は渡しすぎることがないため、子どもも必要以上にお金を使う心配がありません。ただし、頼めばお金をもらえると考えるようになる可能性がある点には注意が必要です。
なぜ必要なのか、いくら必要なのかなどを子どもに説明させ、交渉するスキルを身につけさせてあげることもおすすめです。
報酬制
報酬型は、子どもと取り決めた約束をもとに、お小遣いを渡す方法です。テストで高得点を獲得したら、家事を手伝ったらなど、各家庭によって条件は異なります。
報酬制は、子どもにお金はなにかの対価であることを教えるのに役立ちます。将来的に、バイトや仕事で頑張ればそれだけお金を稼げるという思考を自然に身につけさせてあげられます。
ただし、あまりにも厳しい条件にしてしまうと、かえって子どものモチベーションが下がる可能性がある点には注意しましょう。
子どものお小遣いを決めるポイント

子どもにいつ、いくらお小遣いを渡すのかは、各家庭によって大きく異なります。そろそろ子どもにお小遣いが必要になりそう、現状のお小遣いの制度を変える必要がありそうという人は、以下のポイントを参考にしてみてください。
お小遣いを渡す頻度
まずはお小遣いを渡す頻度を決めましょう。
定額制の場合は、毎月、毎週、毎日など細かく設定できます。子どもがまだお金の管理が難しい場合は、短い頻度で少額ずつ渡すこともおすすめです。
都度制、報酬制の場合も、毎回渡していては保護者も子どももお金の管理が難しくなる可能性があります。月に何回までなど、子どもと一緒にルールを決めておくといいでしょう。
お小遣いを渡す頻度は定期的に見直し、必要であれば頻度を変えていくことも大切です。
お小遣いを渡す方法
お小遣いを渡す方法も大切なポイントです。定額制と都度制、報酬制のどの方法がもっともお金の管理をしやすいか、子どものマネーリテラシーを高められるかを考えてみましょう。
お小遣いを渡す方法は家庭によっても異なるので、周囲の家庭のルールに必ずしも従う必要はありません。子どもと話し合い、最適な方法を選びましょう。
世帯の収入金額
世帯の収入金額によっても、お小遣いの金額は変えていく必要があります。収入が多ければその分お小遣いにも余裕を持たせることができますが、お小遣い以外の支出も考慮しなければなりません。
高収入であっても家賃やガソリン代などの毎月の支出が多かったり、子どもの教育費用を貯金していたりする場合は、お小遣いを調整する必要があります。また、親が高収入だからとたくさんお小遣いを渡すと子どもが努力しなくなる可能性もあるため、きちんとお金の大切さを教えていくことも大切です。
キャッシュか電子マネーか
子どもにお小遣いを渡す際は、キャッシュか電子マネーかを考えましょう。近年は電子マネーが急速に普及していることから、キャッシュではなく電子マネーでお金のやり取りをするケースも増えています。
電子マネーであれば収支の管理がしやすく、子どもがなににお金を使っているか確認できます。また、電子マネーでお金のやり取りをすると金額に応じてポイントを貯めることも可能です。子どもに電子マネーの扱い方を学ばせられる、ポイ活の方法を学ばせられるなどのメリットもあります。
子どもにお小遣いをあげる際の注意点
.jpg?fm=webp)
子どもにお小遣いをあげる際の注意点を解説します。ただお金を渡すだけでなく、マネーリテラシーを高められるような方法も考えてみましょう。
お金の大切さをきちんと教える
子どもにお小遣いを渡す際は、お金の大切さをきちんと教えることを意識しましょう。ただお金を渡すだけでは、子どもは「なにもしなくても親が勝手にお金をくれる」と考えてしまいがちです。結果的に無駄遣いをしたり、お金を得るために努力するという思考に至らなくなってしまう可能性もあります。
お小遣い分の金額を得るにはどれだけの努力が必要なのか、ものを買うときはそれだけの価値があるのかをしっかり考えるべきなど、教えるべきことはたくさんあります。
お金の使い方を見守る
子どもにお小遣いを渡し始めたら、しばらくは子どものお金の使い道を見守ってあげましょう。お金の使い方や大切さを知らない間は、大人の想定外のことにお金を使ってしまう可能性があります。
また、友人間でお金の貸し借りをしてトラブルに発展することもあります。いざというときに対応し、責任を取るのは保護者です。想定外のトラブルを未然に防ぐためにも、子どもにお小遣い帳をつけさせて確認するなどの方法を取り入れましょう。
お小遣いの金額は適宜見直す
子どもにお小遣いを渡し始めたら、その金額は適宜見直す必要があることも理解しておきましょう。年齢だけでなく、物価の上昇や周囲との関係なども考慮する必要があります。
「自分が同じくらいの年齢の頃は〇円もらっていたから同じでいいだろう」という考え方では、子どもの買えるものの選択肢が狭まったり、友人との格差に悩んだりする可能性があります。
周囲の家庭ではどれくらいお小遣いを渡しているのかを聞いたり、上記の平均額を参考にしたりしましょう。
まとめ
お小遣いは定額制のほか、都度制や報酬制などがあり、それぞれにルールも金額も異なります。
保護者が一方的にルールを作ると子どものマネーリテラシーを高められなかったり、不満だけが大きくなったりする可能性があります。お小遣いを渡す際は、子どもとよく話し合って適切な頻度や方法、金額を決定していきましょう。
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。