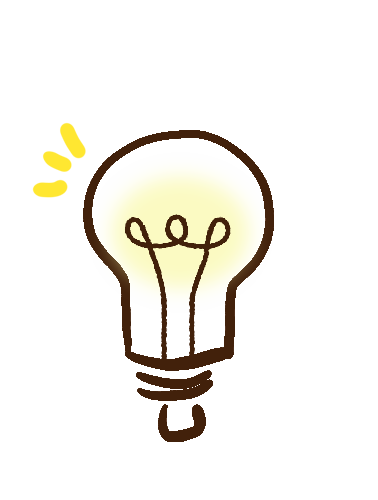外貨預金にかかる税金は?為替差益や確定申告についてもわかりやすく解説
外貨預金で資産を運用したいと考えている人は、税金がどれくらいかかるのかが気になるのではないでしょうか。本記事では外貨預金にかかる税金について説明します。外貨預金で利益が出たら、確定申告が必要なケースがあります。手続きを忘れないように注意しておきましょう。
外貨預金にかかる税金の仕組み

資産運用の方法の一つとして、外貨預金があります。外貨預金とはドルやユーロなどの外貨建てで預け入れる預金です。普通預金と定期預金があり、国内の銀行や信用金庫、外国銀行の日本支店などで取り扱いされています。
外貨預金は日本円の預金よりも高金利になることが多く、為替レートによって為替差益も得られる可能性があるのがメリットです。一方で、元本保証がなく、為替レートの変動やスプレッド(手数料)によって損失が出るリスクもあります。外貨預金は預金保険制度による保護(ペイオフ)の対象外で、金融機関が破綻しても預金は保護されません。
また、外貨預金で利益が出た場合にも税金はかかるため、注意が必要です。
外貨預金で得られる2種類の利益
外貨預金で得られる利益は、「利息」と「為替差益」の2種類に分かれます。
利息
外貨預金の利息は、「利子所得」 に分類されます。円預金と同様に、利息は外貨で支払われ、金利に基づいて計算されます。日本の円預金の金利は低い状態が続いていますが、外貨預金では比較的高い金利が期待できます。
為替差益
為替差益とは外貨建ての金融商品に関して、為替相場の変動によって得られる利益のことです。預入時よりも円安になったときに外貨を売却して円に換金すると、為替差益が生じます。
逆に、預入時よりも円高になったときに引き出して円に換金すると、為替差損が生じます。外貨預金などの外貨建ての金融商品は、為替相場の動向によって元本割れするリスクがあるのです。
利益の種類によって税金のかかり方は異なる
外貨預金の利息と為替差益は、どちらも所得税や住民税の課税対象です。ただし、所得の種類が異なるため、税金の仕組みも異なります。
以下、外貨預金の利息にかかる税金、為替差益にかかる税金のそれぞれについて詳しく説明していきます。
外貨預金の利息にかかる税金

外貨預金をすると、定期的に利息を受け取れます。利息は安定的な収入になりますが、税金が差し引かれることに注意しておかなければなりません。ここでは、外貨預金の利息にかかる税金の仕組みについて解説します。
外貨預金の利息は利子所得
所得は10種類に分類されており、どの所得に該当するかによって税金の計算方法が変わります。外貨預金の利息は、所得の種類では「利子所得」に該当します。円預金の利息も利子所得である点は同じです。
外貨預金はマル優の対象外
「マル優(少額貯蓄非課税制度)」は障害者や遺族年金受給者を対象にした制度で、元本350万円までの預貯金の利息を非課税にできるというものです。外貨預金はマル優の対象外となっています。外貨預金の利息を非課税にすることはできません。
外貨預金の利息は確定申告不要
日本国内において利子所得の支払いを受ける場合には「源泉分離課税」となり、確定申告は不要です。
ですが、海外の銀行にある口座で外貨預金の利息を受け取る場合は、日本での源泉徴収は行われません。そのため、確定申告が必要となります。
源泉分離課税とは
他の所得と分離して一定の税率で税金が源泉徴収され、その時点で課税関係が終了する課税方式です。外貨預金の利息は源泉分離課税であるため、受け取る時点で税金が差し引かれています。外貨預金の利息を受け取っても、確定申告する必要はありません。
税率
外貨預金の利息から源泉徴収される税金の税率は20.315%です。内訳は、所得税等15.315%、住民税5%となっています。
外貨預金で為替差益にかかる税金

外貨預金に資産を預入した場合、為替レートの変動によって為替差益が得られる可能性があります。外貨預金の大きなメリットの一つは、この為替差益による利益が期待できる点です。
ただし、為替差益が発生した場合には税金がかかるため、税務上のルールを理解しておくことが重要です。ここでは、為替差益の税金について詳しく解説します。
為替差益・為替差損とは
外貨建ての取引は、為替相場の影響を受けます。為替相場の変動によって、利益が出たり損失が出たりするのです。利益が出た場合には為替差益、損失が出た場合には為替差損といいます。為替差益、為替差損のそれぞれについて、詳しく説明します。
為替差益の例
次の前提条件で外貨預金の預入・引出をしたと仮定して、為替差益の例を見てみましょう(※計算の簡略化のため、為替手数料については考慮しないものとします)。
前提条件
- 預入時の為替レート:1ドル=130円
- 預入額:1,000ドル
- 引出時の為替レート:1ドル=150円
預入時には1ドル=130円であるため、1,000ドルなら日本円で13万円を預入しています。引出時には1ドル=150円と、預入時よりも円安になっています。1,000ドルを引き出して日本円に戻すと15万円となり、為替差益として2万円を得られるのです。この利益には税金がかかります。
なお、為替差益として課税対象になるのは、外貨を円に戻して利益を確定した場合のみです。預入時よりも円安になっていても、外貨預金のまま保有していれば含み益の状態です。含み益には課税されません。
為替差損の例
続いて、為替差損の例を見てみましょう。前提条件は次のとおりです。
前提条件
- 預入時の為替レート:1ドル=130円
- 預入額:1,000ドル
- 引出時の為替レート:1ドル=100円
預入時に用意したお金は日本円で13万円です。引出時には円高になっており、1,000ドルを日本円に戻すと10万円になります。このケースでは、3万円の為替差損が出ることになります。
為替差益は雑所得
外貨預金で為替差益が発生すると、所得として扱われ、税金がかかります。この為替差益は「雑所得」に分類され、総合課税 の対象となります。
総合課税とは、他の所得と合算し、所得の合計額に応じた税率で課税される方式 です。所得が多いほど、税率も上がる仕組みになっています。
為替差益は原則確定申告が必要
為替差益は雑所得であるため、他の総合課税の所得と合算して税金を計算する必要があります。給与所得のある会社員も、年末調整で雑所得を精算することはできません。雑所得があれば、確定申告する必要があります。
為替差損が出た場合はどうする?
外貨預金の引出を行っても、為替差損が生じている状態なら税金はかかりません。確定申告も不要です。なお、雑所得内では損失と利益を相殺(損益通算)することが可能です。
確定申告することにより、為替差損を黒字の雑所得と相殺して税金を減らせるケースがありますが、雑所得と他の所得との損益通算はできません。為替差損が出ても他の所得から相殺することはできないため、為替差損を翌年以降に繰り越すこともできません。
外貨預金で確定申告が不要なケース

外貨預金で為替差益が出たら、原則として確定申告が必要です。ただし、例外的に確定申告が不要なケースがあります。ここからは、外貨預金で確定申告不要のケースについて説明します。
確定申告不要でも、住民税の申告は必要な場合があります。住民税の申告については、お住まいの自治体に確認してみてください。
給与所得・年金所得以外の所得の合計が20万円以下
自営業者など、もともと確定申告が必要な人は、為替差益が出ても特に手続きは変わりません。一方、会社員や年金受給者など、確定申告の義務がない人は、給与や年金以外の所得(為替差益を含む)が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。
給与所得者の税金は勤務先が源泉徴収、年末調整をします。そのため、次の条件をすべて満たしていれば、確定申告は必要ありません。
給与所得者で確定申告不要の人
- 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下
- 給与の年間収入金額が2,000万円以下
- 給与の支払いは1ヶ所のみから受けている
- 給与の全部について源泉徴収されている
年金受給者には確定申告不要制度が設けられています。次の条件をすべて満たしている年金受給者は、確定申告不要です。
年金受給者で確定申告不要の人
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、すべてが源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
為替差益と給与・年金以外の所得を合計して20万円以下の人であれば、確定申告は不要です。
年間の所得が48万円以下
為替差益を含めたすべての所得が年間48万円以下の人も、確定申告は必要ありません。所得税を計算するときには基礎控除として48万円を所得から差し引きできます。年間所得が48万円以下であれば、課税所得が0円となり、税金はかかりません。
まとめ
外貨預金で得られる利益は利息と為替差益の2つに分かれます。利息は源泉分離課税となっており、金融機関で税金が徴収されています。一方、外貨預金を引き出して為替差益が出た場合には、原則として確定申告が必要です。為替差益が出ていても確定申告しなくても良いケースもあるので、よく確認しておきましょう。
投資信託のご留意事項(必ずご確認ください)
商号等:株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
外貨預金のご留意事項(必ずご確認ください)
商号等:株式会社西日本シティ銀行
■あわせて読みたい記事
・外貨預金のメリット・デメリットを徹底解説!不安を解消してから始めよう
・外貨預金の初心者さんでも大丈夫!わかりやすく教えちゃいます。
・外貨預金の入金のタイミングは?メリットやデメリット、運用のコツなどを解説
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

AFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士、夫婦カウンセラー
大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。