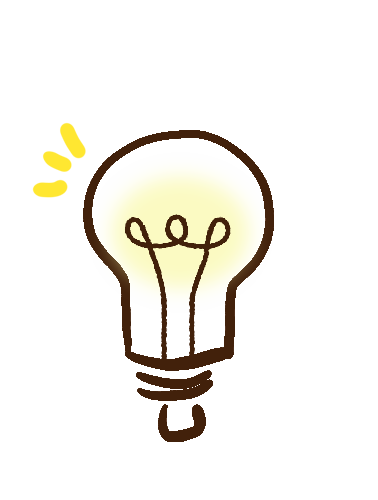年金の平均受給額はいくら?国民年金と厚生年金それぞれの計算方法も解説
日本の年金制度は現役世代が保険料を支払い、それを高齢者の年金給付に充てる仕組みで成り立っています。近年は少子高齢化が社会問題となっており、自分がどのくらい年金をもらえるのか気になる人も多いのではないでしょうか。本記事では年金の平均受給額や増やし方などについてまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
老後に受け取る年金の種類

年金には国民年金や厚生年金などの「公的年金」と、任意加入で公的年金に上乗せする「私的年金」があります。年金受給額を確認する前に、それぞれの年金の仕組みや特徴について理解しておきましょう。
公的年金
公的年金は、日本国内に住むすべての人が原則として加入する制度で、国が運営しています。公的年金にはすべての人が対象となる国民年金と、会社員や公務員などが上乗せで加入する厚生年金があり、この2つが日本の年金制度の基盤となっています。
国民年金
日本に住む20歳から60歳未満までのすべての人が加入を義務付けられている公的年金制度です。自営業者や農業、漁業従事者は国民年金の第1号被保険者として、保険料を自分で納めます。
一方、会社勤務や公務員の人は国民年金の第2号被保険者となり、国民年金に加入していても保険料を直接納めることはありません。厚生年金保険や共済組合が代わりに費用を負担しているためです。
厚生年金
会社や公的機関に勤務している人が加入する年金制度です。日本の公的年金は国民年金と厚生年金の2階建て構造になっています。厚生年金の保険料は収入に保険料率を掛けた額で、勤務先がその半額を負担する仕組みです。
厚生年金は70歳まで加入可能です。受給額は加入月数と加入期間中の収入額に応じて決まるため、現役時代の収入が高い人ほど老後の受給額も高くなります。
私的年金
私的年金は、公的年金に上乗せして給付される加入義務のない年金です。大きく分けると、加入期間に応じてあらかじめ給付額が定められる確定給付型と、拠出した掛金+運用益の合計額を給付する確定拠出型があります。
確定給付企業年金
企業が従業員の同意を得て年金資産を積み立てて管理・運用し、従業員が退職後あらかじめ定めた内容に基づいて給付が受けられる年金制度です。この制度を実施している企業に勤務する従業員のみが対象となります。
確定拠出年金
事業主や加入者が一定額の掛金を拠出し、その運用結果に基づいて給付額が決定される年金制度です。企業型は企業が掛金を拠出して従業員(加入者)が運用し、個人型は加入者が自ら拠出・運用します。
なお、iDeCoとは個人型確定拠出年金の愛称です。
◾️あわせて読みたい記事
確定拠出年金にかかる税金は?計算方法や受け取り方をわかりやすく紹介
国民年金基金
厚生年金に加入できない自営業やフリーランスなど、国民年金第1号被保険者や国民年金に任意加入している人を対象とした公的な年金制度です。国民年金に上乗せできるため、受け取れる年金額を増やせます。20歳から年金受給が始まる65歳未満まで、いつでも加入可能です。
個人年金保険
個人が公的年金に上乗せする目的で加入する民間の保険会社の商品で、運用方法や受取期間などは自分で選べます。契約時に決めた年齢まで毎月保険料を支払い、それを原資として一定期間または一生涯年金を受け取れる私的年金です。
年金受給額の平均ってどのくらい?
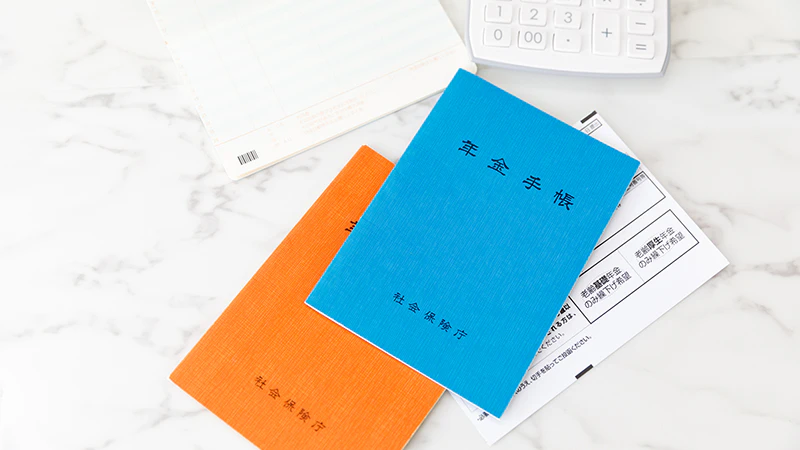
ここでは、日本国内に住むすべての人が原則加入する公的年金の平均受給額を紹介します。
公的年金の平均受給額
厚生労働省の資料によると、2023年国民年金(老齢基礎年金)の平均受給額(月額)は57,700円でした。平均受給額が満額(40年間納付)の66,250円よりも低いのは、学生のときに年金保険料を払っていない、支払い免除を受けたなどが理由として考えられます。
また、同年の厚生年金(老齢厚生年金)の平均受給額(月額)は147,360円で、2022年まで減少傾向でした。2023年に上がりましたが、これは改定により年金額の引き上げがあったためです。
参考元:厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
年代別の平均受給額
厚生労働省の資料をもとに、国民年金と厚生年金の年代別の平均受給額を表にまとめました。国民年金の平均受給額は若い世代の方がやや高めですが、厚生年金の平均受給額は若くなるほど減る傾向にあることがわかります。
65歳未満の平均年金受給額が低いのは繰上げ受給をしているためです。厚生年金の場合、1985年の法改正で受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられましたが、支給額は減額傾向が続いています。
年齢別老齢年金受給権者数及び平均年金月額(2023年度末現在)
| 厚生年金 | 国民年金 |
|---|---|---|
60~64歳 | 75,945円 | 44,836円 |
65~69歳 | 147,428円 | 59,331円 |
70~74歳 | 144,520円 | 58,421円 |
75~79歳 | 147,936円 | 57,580円 |
80~84歳 | 155,635円 | 57,045円 |
85~89歳 | 162,348円 | 57,336円 |
90歳以上 | 160,721円 | 53,621円 |
年収別の平均受給額
年収によって受給額が変わるのは厚生年金のみです。国民年金(老齢基礎年金)の受給額は、保険料の納付月数で決まります。国民年金の満額は毎年変わりますが、2025年は年額831,696円で、月額にすると69,308円です。
この金額に年収ごとの厚生年金受給額を加え、加入期間40年間(480カ月)とした場合の公的年金受給額の違いをまとめたものが、以下の表です。なお、年金受給額の詳しい計算方法については次項で解説します。
年収別の公的年金受給額(月)
年収 | 国民年金(老齢基礎年金) | 厚生年金(老齢厚生年金) | 年金受給額/月 |
|---|---|---|---|
300万円 | 69,308円 | 54,810円 | 124,118円 |
400万円 | 69,308円 | 72,349円 | 142,388円 |
500万円 | 69,308円 | 92,081円 | 160,658円 |
800万円 | 69,308円 | 146,891円 | 215,468円 |
この表では経過的加算、加給年金は考慮していません。その他、家族構成など条件によって金額は変わりますが、平均年収が高い人ほど厚生年金の平均受給額は増加します。
参考元:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
参考元:日本年金機構「報酬比例部分」
年金受給額の計算方法

年金の受給額は働き方や加入期間によって異なります。ここでは、老後に受け取る老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)の受給額がどう決まるのか、それぞれの計算式についてまとめました。
老齢基礎年金(国民年金)の受給額計算
老齢基礎年金の受給額は年収には関係なく、保険料の納付期間で決まります。計算式は以下のとおりです。
老齢基礎年金の受給額=年間の支給額(毎年改定)×保険料納付済月数÷480ヵ月
計算式からわかるように、40年間(480ヵ月)納付した人は満額受給できますが、40年未満だと減額になります。また、期間内に納付の免除を受けていると以下の割合で減額されるので、注意が必要です。
● 全額免除:全額免除月数×4/8
● 4分の1納付:4分の1納付月数×5/8
● 半額納付:半額納付月数×6/8
● 4分の3納付:4分の3納付月数×7/8
参考元:日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
老齢厚生年金(厚生年金)の受給額計算
老齢厚生年金は保険料を納めた月数だけでなく、給与や賞与など現役時代の収入に応じて受給額が決まります。計算式は以下のとおりです。
老齢厚生年金の受給額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額
報酬比例部分
報酬比例部分とは年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まるもので、以下のように加入期間を分けて計算します。
A:2003年3月以前の加入期間 | 平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの加入期間の月数 |
B:2003年4月以降の加入期間 | 平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数 |
※報酬比例部分=A+B
平均標準報酬額とは、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を厚生年金に加入した期間の月数で割った額のことです。
経過的加算
経過的加算とは、厚生年金を納付した期間のうち老齢基礎年金の金額に反映されない期間(例えば20歳未満や60歳以降)がある場合、その期間に応じて老齢厚生年金に上乗せして相当額を補う仕組みです。
加給年金額
加給年金は被保険者期間が20年以上の人が65歳の時点で配偶者または子を扶養している場合、老齢厚生年金に加算される年金のことです。
参考元:日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
参考元:日本年金機構「報酬比例部分」
年金受給額のシミュレーション
国税庁の調査(2023年分)によると、給与所得者数の平均給与は約460万円で、男女別では男性が約569万円、女性は約316万円となっています。
この数値をサンプルデータとして、公的年金の受給額がどのくらいになるのかを、以下の条件で単身者や夫婦などのケースに分けて比較しました。なお、本シミュレーションでは経過的加算や加給年金額は考慮していません。
● 国民年金は満額=40年間(480カ月)支払で、年間支給額は83万1696円(2025年度)
● 老齢厚生年金(年額)= 平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 厚生年金加入月数(480カ月)
単身会社員のケース(平均年収460万円)
| 年間受給額 | 受給額/月 |
|---|---|---|
国民年金 | 831,696円 | 69,308円 |
厚生年金 | 999,734円 | 83,311円 |
年金受給額 | 1,831,430円 | 152,619円 |
単身会社員の年金受給額は、152,619円/月になります。
共働き夫婦のケース
夫(平均年収569万円)
| 年間受給額 | 受給額/月 |
|---|---|---|
国民年金 | 831,696円 | 69,308円 |
厚生年金 | 1,236,514円 | 103,043円 |
年金受給額 | 2,068,210円 | 172,351円 |
妻(平均年収316万円)
| 年間受給額 | 受給額/月 |
|---|---|---|
国民年金 | 831,696円 | 69,308円 |
厚生年金 | 684,029円 | 57,002円 |
年金受給額 | 1,515,725円 | 126,310円 |
共働き夫婦の年金受給額の合計は298,661円/月になります。
会社員+専業主婦(夫婦)のケース
夫(平均年収569万円)
| 年間受給額 | 受給額/月 |
|---|---|---|
国民年金 | 831,696円 | 69,308円 |
厚生年金 | 1,236,514円 | 103,043円 |
年金受給額 | 2,068,210円 | 172,351円 |
妻(平均年収0円)
| 年間受給額 | 受給額/月 |
|---|---|---|
国民年金 | 831,696円 | 69,308円 |
厚生年金 | 0円 | 0円 |
年金受給額 | 831,696円 | 69,308円 |
夫婦(会社員+専業主婦)の年金受給額の合計は241,659円/月になります。
年金の受給額は、働き方や年収などにより変わります。ねんきん定期便がある人は、厚生労働省の公的年金シミュレーターを使えば自身の受給額を試算可能です。
老後の年金を増やす方法

昨今は物価高が続いており、老後の年金生活に不安を感じる人も多いでしょう。そこで、将来に備えて年金を増やすための方法を紹介します。
国民年金の任意加入
国民年金の加入期間は20歳から60歳までの40年間です。しかし、保険料の免除や納付猶予を受けた期間がある人は、満額受給できません。
そのような場合、国民年金に任意加入することで年金を増額できます。60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きが可能で、申し込み窓口は居住地の役所(役場)の担当部署や最寄りの年金事務所です。
年金の繰下げ受給
公的年金の受給開始は原則65歳からですが、受け取りを遅らせることで受給額を増やせます。これを年金の繰下げ受給といい、老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれも繰下げ受給が可能です。
増減率は繰り下げた月数×0.7%で計算され、75歳まで最大84%年金受給額が増えます。66歳以降に繰下げ受給の請求手続きが可能になりますが、その時点で繰下げ増額率が決まってしまうため注意が必要です。
私的年金で上乗せ
私的年金は老後の生活が不安という場合に任意で加入し、公的年金に上乗せできる年金制度です。私的年金には企業年金と個人年金がありますが、ここでは会社員以外も対象の個人年金に絞って紹介します。
国民年金基金
自営業やフリーランスなど、厚生年金がない国民年金第1号被保険者が生涯の年金収入を増やせる制度です。掛金の上限は月額68,000円で、1口目は終身年金、2口目以降は終身年金または確定年金のどちらかを選べます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
自分で設定した掛金を拠出し、選択した金融商品を運用して、60歳以降に年金として受け取る制度です。掛金は全額所得控除の対象で、運用益はすべて非課税になります。また、受け取りの際は退職所得控除や公的年金等控除の対象となり、節税効果が期待できます。
個人年金保険
民間会社の個人年金保険を利用する私的年金です。契約時に定めた年齢まで保険料を支払い、一定の年齢になると年金として受け取れます。確定年金・有期年金・終身年金の3種類の受け取り方法を契約時に選択可能です。また、一定の条件を満たすと一般生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除が受けられます。
老後に向けた資産形成
最近はお金を銀行に預けておくだけでなく、投資や資産形成を積極的に行っている人が増えています。ここでは、その中でも年金対策としておすすめできる金融商品を紹介します。
NISAを利用
NISA(少額投資非課税制度)は、年金対策として大変有効な金融商品です。投資商品のため元本割れリスクはありますが、投資で得た利益は非課税になります。つみたて投資枠と成長投資枠を選べ、いつでも引き出し可能なので柔軟に運用できます。
銀行の定期預金
銀行には「年金定期預金」という金融商品があります。これは、公的年金の受取口座に指定することを条件に、通常より金利が上乗せされる定期預金です。
西日本シティ銀行にも「年金ココロ定期預金」があります。1年ものスーパー定期・スーパー定期300に金利が上乗せされ、その他に特典などもあるため、興味のある人は検討してみてください。
まとめ
従来の年金の仕組みだけでは老後が不安という人は多いでしょう。どうすればよいかわからない場合は、まず将来どのくらい年金を受け取れるのか試算してみてください。老後のための資産形成は、公的年金以外にもいくつか方法があります。私的年金や節税できる金融商品などを上手に活用して、早めに準備しておきましょう。
※LIFUQU noteのサイトポリシー/プライバシーポリシーはこちら。

髙井 美智彦
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学卒業後、システムエンジニアを経て通信機器商社の経営戦略室で新規事業の立ち上げに参画。退社後はシステム会社の代表取締役に就任し、パソコン通信サービスを展開。1996年に著書『わかる!イントラネット』執筆後はフリーランスとして活動。事業経験とFP資格を活かしビジネス系ライターとして複数メディアで執筆中。